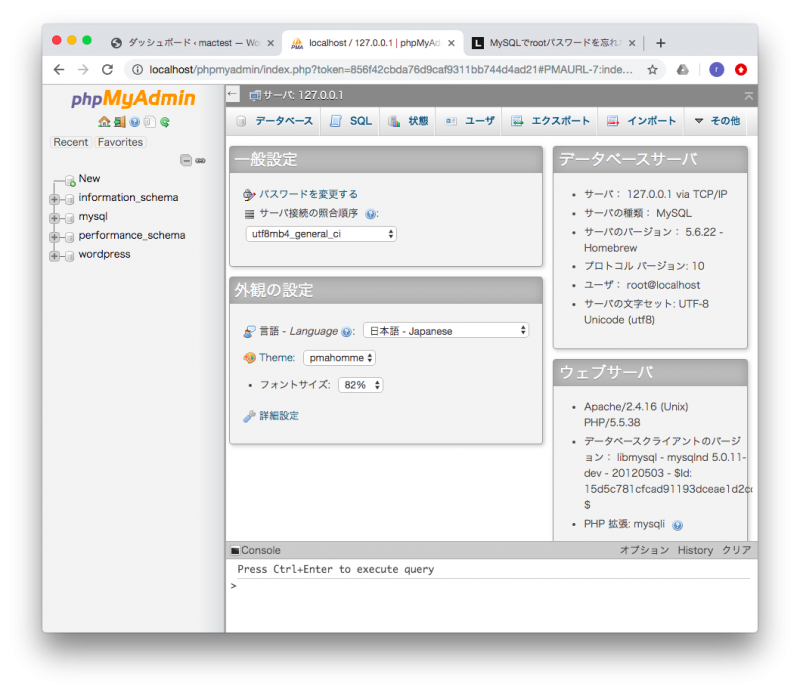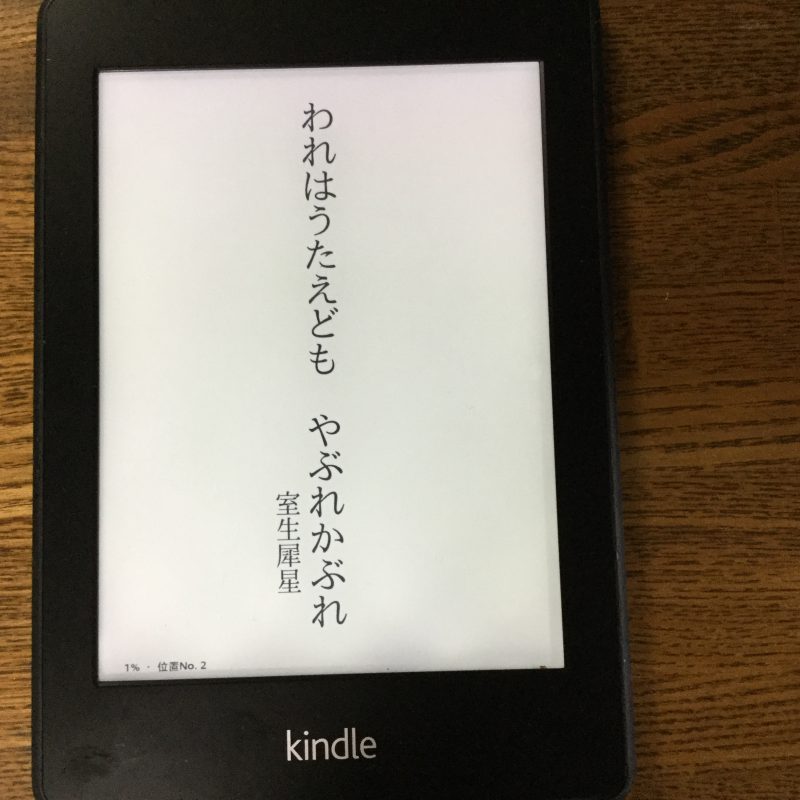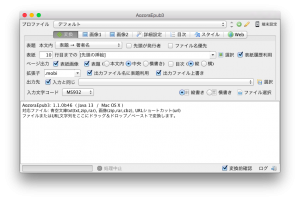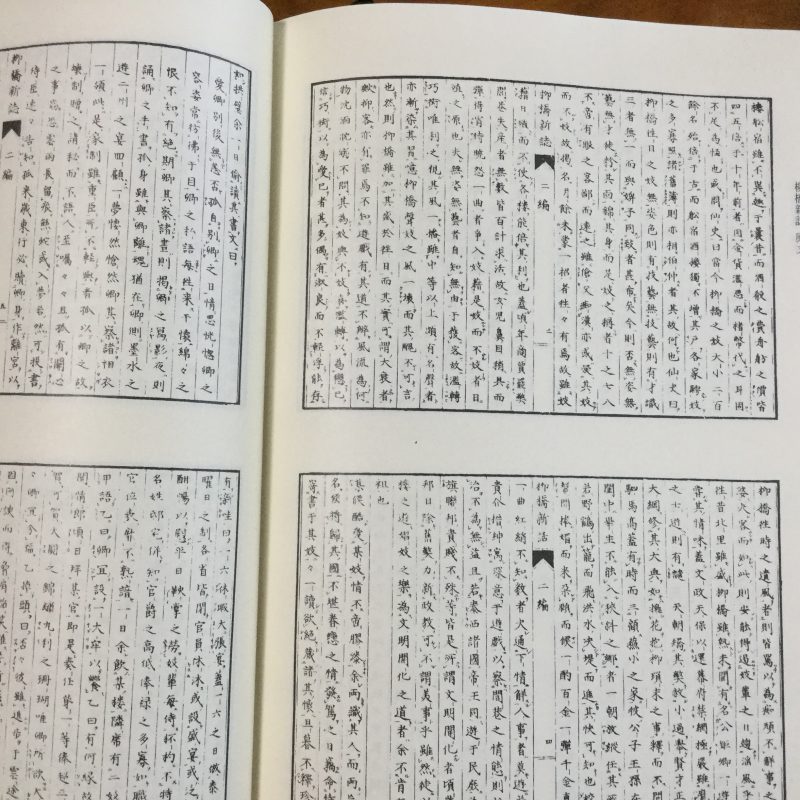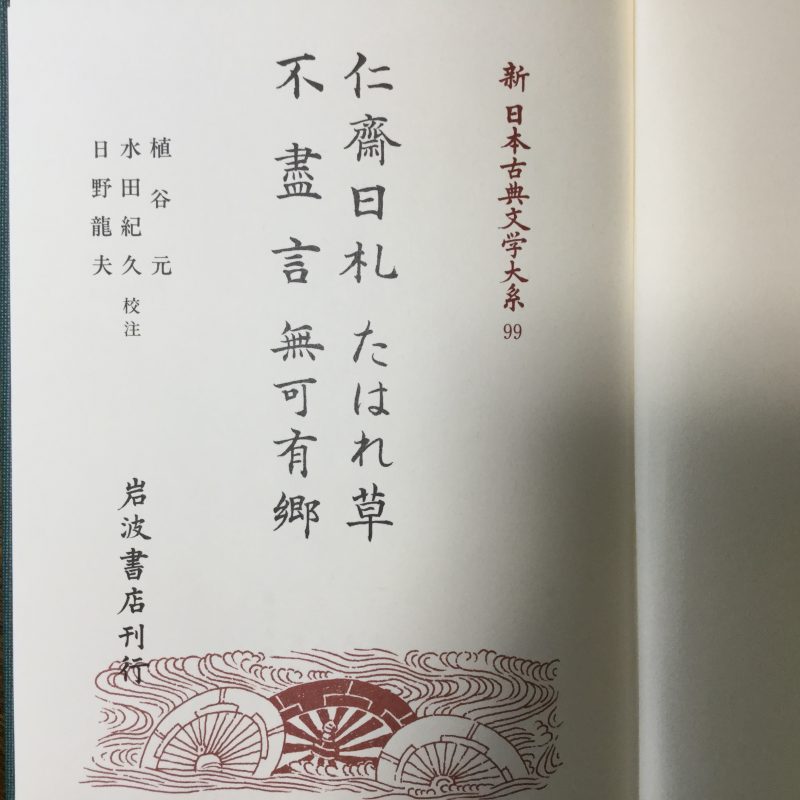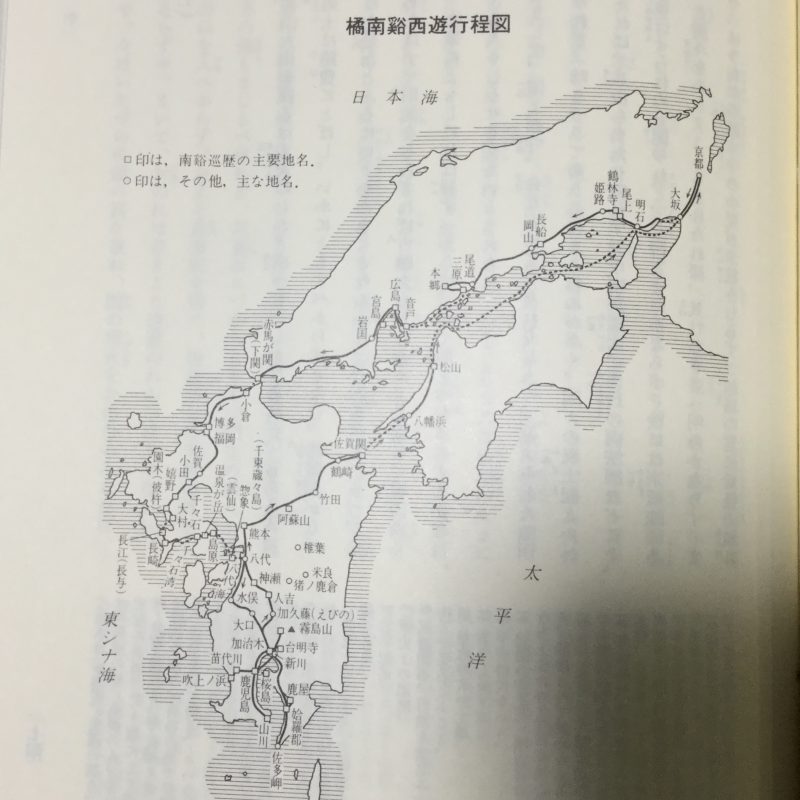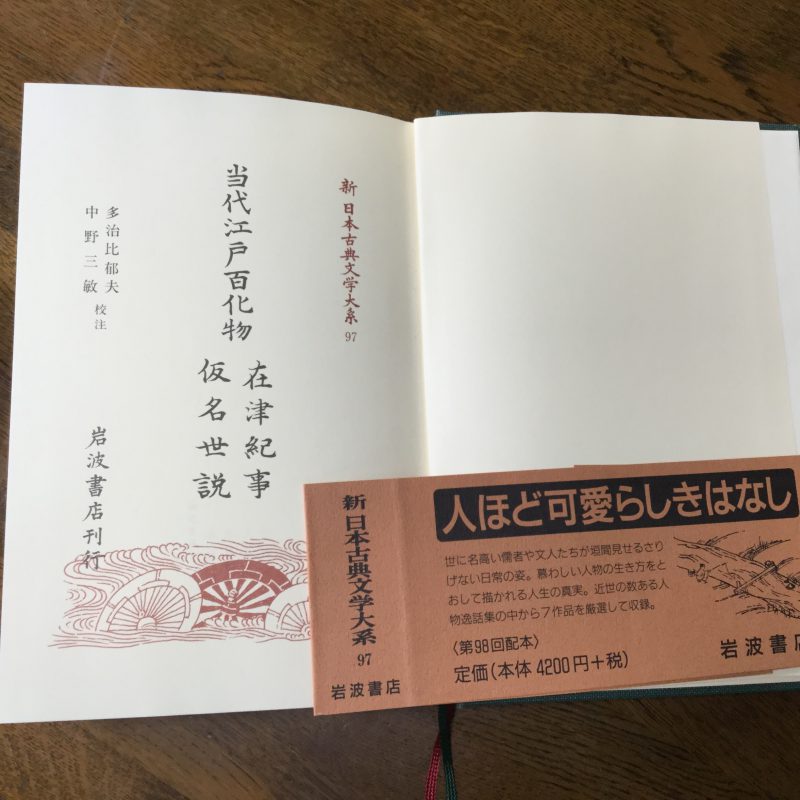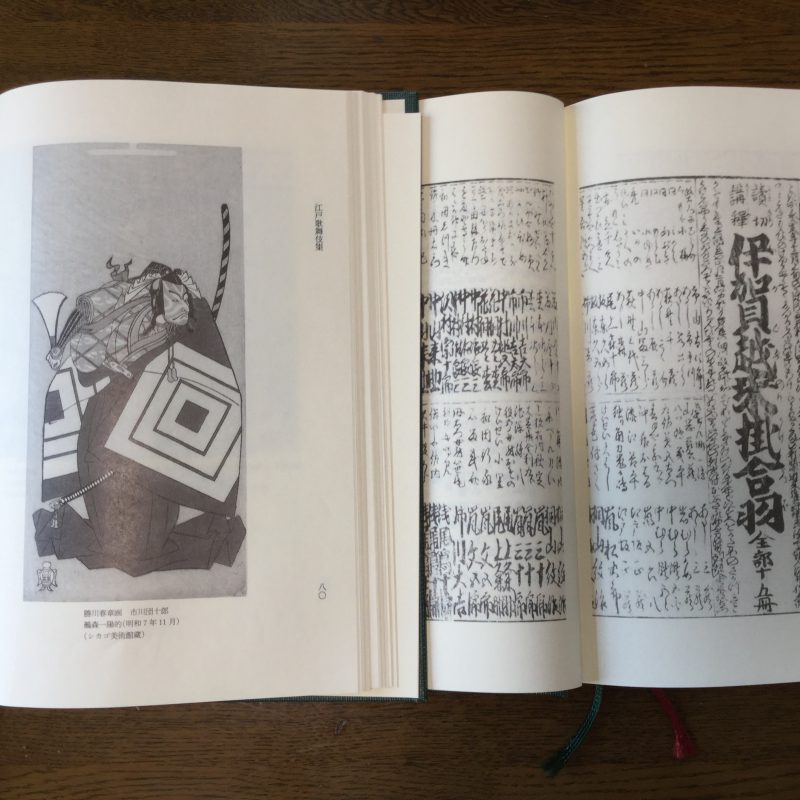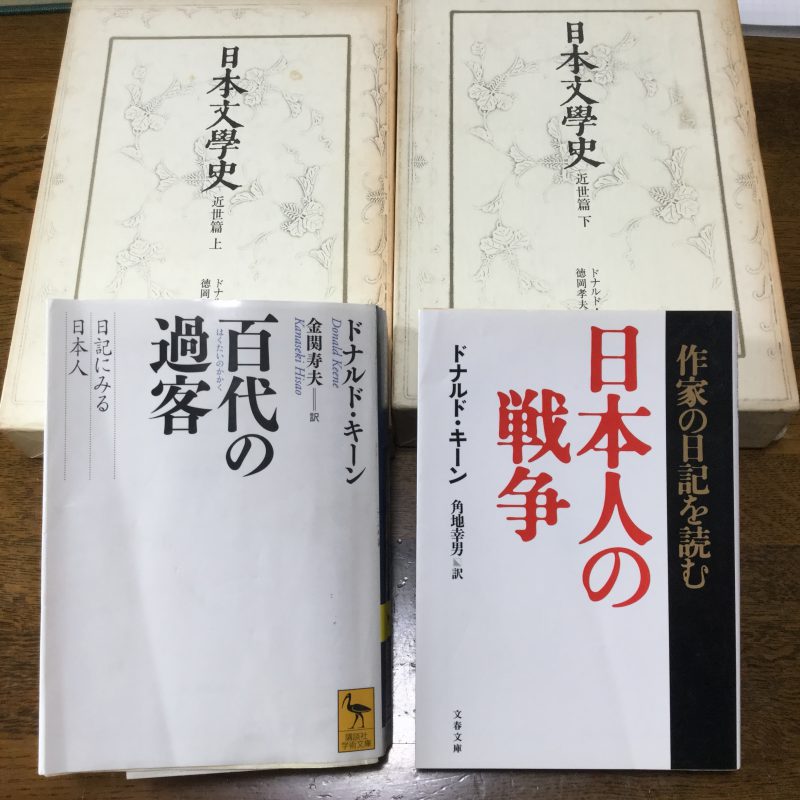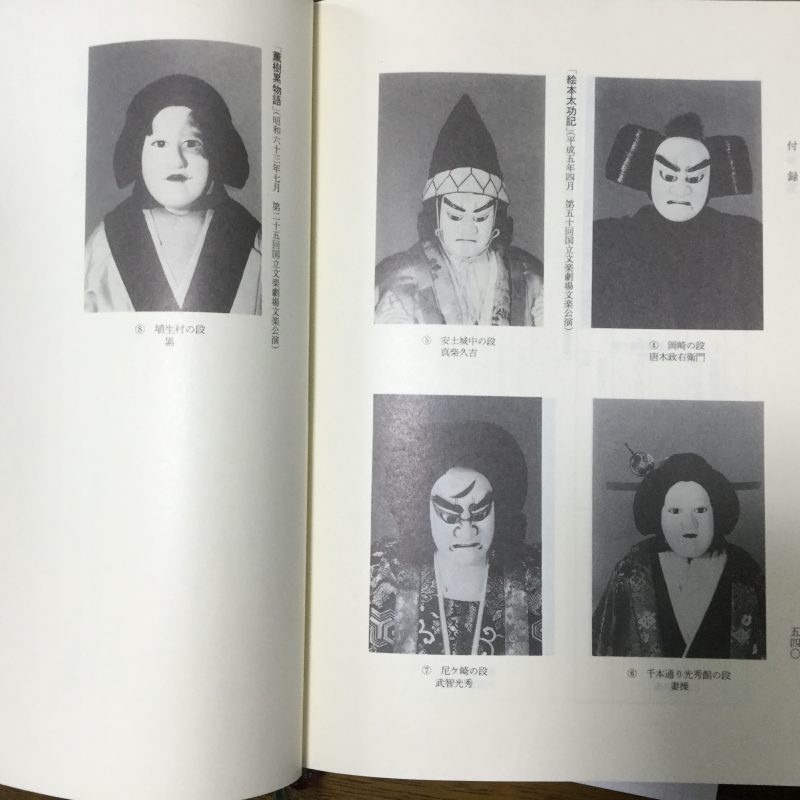この記事を書くきっかけになったのはクラウドサービスの一つDropboxで、ある事故?があったからだ。
クラウドサービスは便利
クラウドサービスは便利だ。複数のデバイスを使っている人が多いと思うが、一つのファイルを複数のデバイスで見るにはクラウドが欠かせない。
かく言う私も、自宅にはウィンドウズのデスクトップパソコンがあり、外出用にはMacBookとiPadmini(自宅で使うiPadの旧型もある)があり、さらにはLinuxが走るネットブックパソコンを持っている。ここまで多くないにしてもパソコンとスマホを持っているという人は多いと思う。例えばスマホで撮った写真を自宅のPCで見るといった場合、クラウドに置いておけば、ネット環境さえあれば簡単だ。写真だけでなくPCで作った書類をスマホやパッドで参照したり、訂正したりもできる。さらに他の人と共有機能を使って、ファイルのやり取りもできる。
クラウドサービスには様々ある
さて、クラウドサービスといっても多くの種類がある。私が使っているものをあげると以下だ。(もちろん他にもあるが)
- Dropbox
- GoogleDrive
- OneDrive
- iCloud
- Amazonphotos
- SakuraPocket
(上の四つは無料版を使っている。下の二つはいわば有料だが、アマゾンのプレミア会員かさくらサーバーの契約者ならそれ自体は無料で使える。)
さて、それぞれには特徴があるのだが、それを私の経験から書いておく。
Dropbox
まずこれを一番使っている。私はこのサービスをかなり早い時期から使っていて、多くの友人達に紹介してきた。そのおかげで無料版ながら12.8Gの容量を持っている。そして共有機能を多く使い、講習の為のファイルなどをやり取りしている。確かに便利に使ってきた。
問題点1 共有と容量の問題
しかし、この共有が曲者だ。実はある時Dropboxが仕様変更をした形跡がある。かつて共有部分は所有者のみ容量は食うが、他の共有者の容量を圧迫しなかったはずだ。しかし、そうではなくなっている。所有者以外の共有者の容量も食ってしまうのだ。講習で使うフォルダをある人と新たに共有したところ、その人が持っている容量を超えてしまい。なんとアクセス不能になってしまったのだ。
問題点2 容量超えの問題
この容量超えがあるとアクセス不能になる仕様は問題だ。もちろん警告は出るのだが、有料版に誘うのが主な目的になっている。こんなケースもあった。あるメーカーのPCを購入したところなんと1TのDropboxが付いていた。そこでいろいろとファイルを保存していたが、それが1年限りだあった為に元の無料版の容量に戻ってしまい、これまたアクセス不能。そこで有料版に誘われ結局有料版に切り替えたと言うケースだ。
問題点3 削除と復元機能がわかりにくい
私はこの件以来、Dropboxの中身を整理することにした。いろいろなフォルダに同様なファイルがあったり、共有フォルダをいろいろ作ったりしていたからだ。もちろん容量が足りなくなりつつあったこともある。ネットのDropbox上で行うのは難しかったので、PC上で同期しているファイルを整理して反映させる形をとった。これが実に時間がかかった。しかも他のデバイス上での反映が困難だった。これはある意味仕方がないことことかもしれない。いわゆる「同期」という機能がよく理解できていなかったとも言える。削除はネット上で行うのがベストだ。そうすればすべてのデバイス上から削除するかという警告がでる。そして復元機能だ。これがあるのは助かるが、実は切り過ぎてしまい必要なファイルが消えてしまったので復元をすることにした。ところがネット上では削除ファイルを個々に示してくれないのだ。「何々とその他ファイル何件」といった具合だ。大きく復元し、不必要なファイルをまた削除するという手間となった。
問題点4 カメラ自動アップロードは落とし穴だ
これは決して使ってはいけない。特に共有者にも周知させる必要がある。それとMac系のデバイスを使っている共有者には画像の削除について言っておくべきことがある。こんな事例だ。ある時Dropboxをあけたら大量の見知らぬ画像がアップされていた。調査してわかったのだが、ある共有者がPCに画像が入っているメモリーを指して、カメラ自動アップロードを許可してしまったのだ。またあるべき画像が幾つか消えていたことがあった。これはiPhoneである共有者が思い切り「写真」を削除した為に起こった。Mac系のデバイスではあらゆるところにある画像を「写真」という形でまとめている。共有して同期しているフォルダにある画像も「写真」の一部なのだ。
このカメラ自動アップロードはなんといっても容量を食う最大のものだ。これを許可しているとすぐに容量をオーバーしてしまう。となれば有料版にいざなえる。向こうも商売だから。
問題点5 台数制限が導入された
最後にこれも最近の仕様変更だが、台数制限が導入されたことだ。3台までとなった。ほとんどの人はこれでも大丈夫だろうが、私などは5台を使いまわしているのだから困ることになる。さっそく旧型のiPadからはDropboxを削除した。
結論
さてこれまでいろいろと難点ばかり言ってきたが、いずれも使用者の注意で防げるものばかりかもしれない。無料で使うにはそれだけ落とし穴があるということだ。中途半端な理解で使うと痛い目にあいますよということかもしれない。以下の点だけは注意すべきだと思う。特に初心者に紹介する場合は気をつけよう。
- カメラ自動アップロードは使わない。
- 同期は選択同期にする。
- 共有は共有者に「共有ポリシー」を理解してもらう。
- 常に容量のチェックをする
こうすればやはり便利に使えるはずだ。
GoogleDrive
これもこれまでよく使ってきた。無料で15GあるのでDropboxの無料版よりかなり多い。しかしこれも容量オーバーに近づいた経験がある。
問題点1 アカウント全体で15G
実はドライブにはそんなにファイルを置いていなかった。あれと思った。実はGメールが問題だったのだ。Gメールはこれまであらゆる場面で使ってきた。しかもメールそのものを削除してこなかった。このGメールは全くと言っていいほどスパンメールが来ない。プロバイダのメールでは考えられないほどだ。そこで古いメールも検索してみる必要があるので数年間削除しないでほっておいたのだ。これが原因だった。つまりこの15Gはアカウント全体でのようだったのだ。削除してことなきをえたが、これをまず認識しておかなければならない。
問題点2 googleフォトの容量制限がわかりにくい
GoogleDriveとはべつだが、googleフォトが人気だ。実は私は使っていないのだが、これについても触れておく。googleフォトは無料で無制限を謳っている。ほんとかいなって気がするけど、実はアップするファイルに制限があるのだ。「高品質」を選択すれば無制限だが、元のサイズを選択するとアカウント内の制限に触れることになる。つまり例の15G以内だ。「高品質」というのは保存の際圧縮されるということだ。うまい命名だと思うが、オリジナルのサイズで保存してくれないということでもある。
結論
グーグルのサービスに対してはかなり好感をもっている。やたらと有料版に誘うことも少ないし、メールのセキュリティ機能も優れている。これはグーグルがここに挙げられている情報を別な形で使っているからでもある。ビックデータというやつだ。もっと言えば個人情報を使っているということになる。無料には訳がある。この辺りをしっかり認識して、納得できれば使うべきだろう。
OneDrive
これはマイクロソフトのクラウドサービス。このサービスの最大の魅力はマイクロソフトオフィスとの連携にある。PC上で作成したファイルをここに置いて、パッドなどで参照修正できる点だ。また共同作業もできる。ただ、無料版は5Gと容量は少ない。これはかつて15Gあったものを減らしてきた訳だ。有料版に誘う気満々と言える。またオフィスそのものを365版にしたいという欲求があり、これに契約していれば無制限としているのもその表れだと言える。
問題点 実は不具合が多く報告されている
私が実際に遭遇した訳ではないが(実際にはあまり使っていないんで)、ネット上に不具合の報告が散見される。マイクロソフト自身も
「最近の OneDrive の問題に関する修正プログラムと回避策」(最終更新日: 2019 年 6 月 11 日)
という情報をあげている。
これを見ると実際に業務で使えるのかという疑問を持たざるを得ない。
iCloud
これはMacが行っているサービス。無料版は5Gと少ない。このiCloudの最大の問題はなんでもこれを使いなさいという姿勢だ。「バックアップができていないからiCloudでしなさい。ただ、容量が足りませんよ」とくる。こんな事例があった。iPhoneで写真をたくさん撮り、iCloudに上げていた。あっという間に無料版の容量を超えてしまう。有料版に誘われる。しかも課金情報を登録している場合(クレジットカードを登録)が多いので、簡単に有料版と契約することになる。しかも少しづつだ。
問題点 MacはMacの中でやりなさい
実はパソコンにバックアップも取れるし、写真もパソコンに保存できる。だが、これがまたやりにくい仕様になっている。パソコンへのバックアップはiTunesというアプリを使わなければならない。このアプリ、ウィンドウズ版もあるのだが、アップデートがうまくいかない場合がある。写真のパソコンへの保存もウィンドウズでやる場合コツがいる。たとえばiPhoneをUSBで接続してもデバイスとして認識されない場合がある。これはiTunesでの設定によるのだ。うまくやれば写真のみはコピーできるが、初心者にはむずかしい。もちろんパソコンがMacであれば問題はない。それどころか、いとも簡単にできる。
ウィンドウズユーザーでiPhoneやiPadを使っている人は増えていると思うが、不親切だと言わざるを得ない。
Amazonphotos
さて、今度は有料サービス。しかしちょっと変わった課金の仕方だ。アマゾンのプレミアム会員なら無料と謳っている。プレミアム会員は年額3000円取られるからこれだけを考えると完全な有料サービスだ。ただ、写真については容量無制限だある。しかもグーグルフォトのように圧縮なしだ。保存だけでなく様々な機能を持っている。PC上にある写真をバックアップするには適しているし、整理がうまくできる。もちろん他のデバイスで見ることもできる。私は写真はもっぱらiPadで撮っているが、数が多くなるとパソコンに移している。フォルダも幾つかに分けて保存している。これをバックアップする訳だ。そうすると複数のフォルダで保存し、バックアップした写真がいろいろな形で並び替えて表示される。年代別が便利だ。また検索もいろいろな形でできる。
問題点 動画は容量制限がある。
しかし、問題はプレミアム会員をずっと続けなくてはならないという点だけでなく、動画の保存に制限がある点だ。5Gまでとなっている。これを超えるとさらに課金が生じる。保存する際に「写真のみ」とはっきりさせなくてはならない。これも一種の引っ掛けのような気がする。
問題点 容量無制限がいつまで続くかわからない
このサービスはあまりアマゾンが宣伝していない。大々的に宣伝するとサーバーの用意が大変になるからだろう。したがってこれが広まると制限が出てくる可能性がある。したがってあくまでバックアップという意識で使うべきだろう。
Sakurapoket
これもある意味有料サービス。さくらレンタルサーバーのサービスだ。もともとサーバーを契約していて、ウェブで容量を全て使っていないなら、空いたところにファイルを置くことはできる。ただ、これではクラウドサービスのように使うことはできない。それを他のサービスと同様に使えるようにしたのがこの「さくらポケット」だ。容量は契約によって違うが、基本的なスタンダードの契約なら100Gからウェブ等で使用している分を引いた容量ということになる。実はウェブ等ではそれほど多くの容量を使っていない場合が多い。私の場合は半分の50Gをクラウドとして使っても大丈夫な気がする。スタンダードは月額515円だからサーバー代としてはそれほど高いものではない。
使い勝手についてはアプリを使っていないのでなんとも言えない。FTPでファイル転送ができるのは当たり前だが。
まとめ
以上ダラダラと書いてきたが、これまで書いてきたことは私の経験から得たもので、必ずしも一般論ではない。ただ、言えることは便利なクラウドサービスも使い様だということだ。それぞれに特徴があり、落とし穴がある。この辺りを参考にしていただければ幸いだ。
2019.07.16