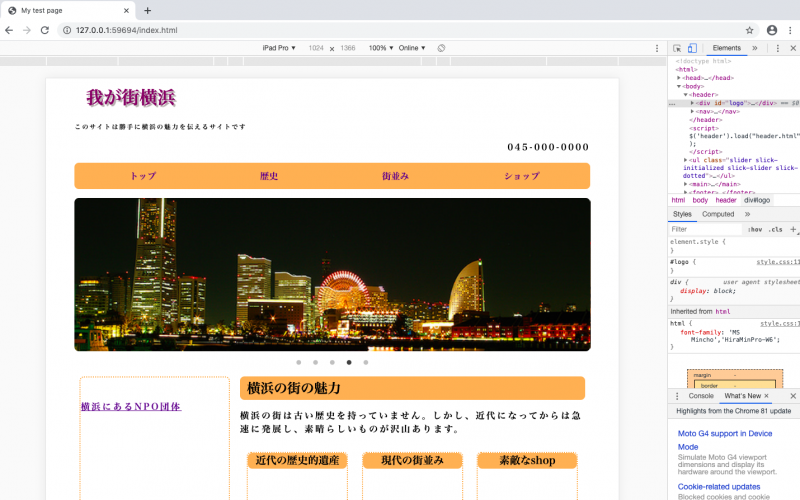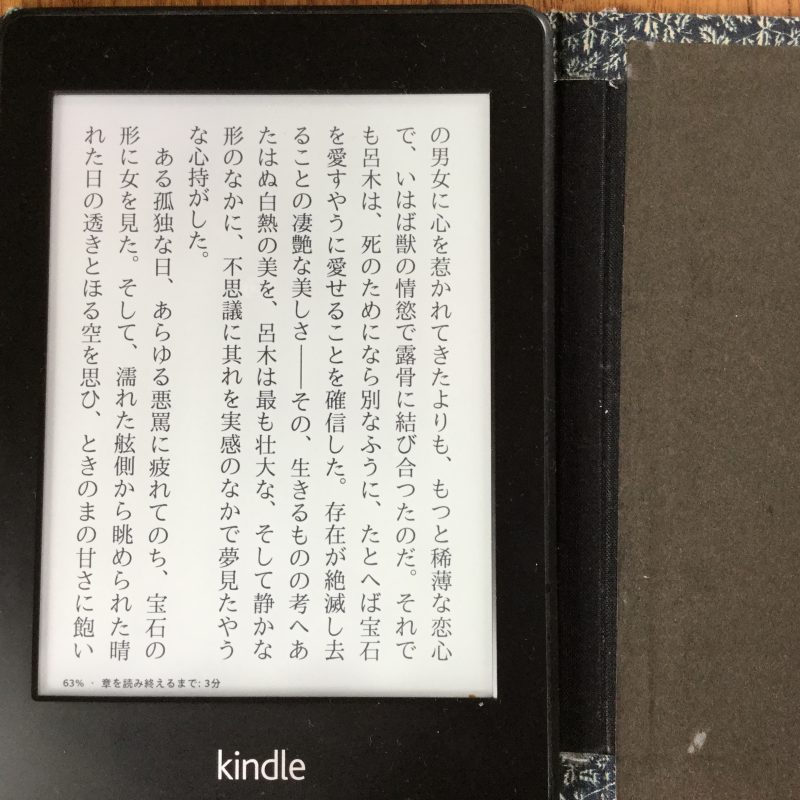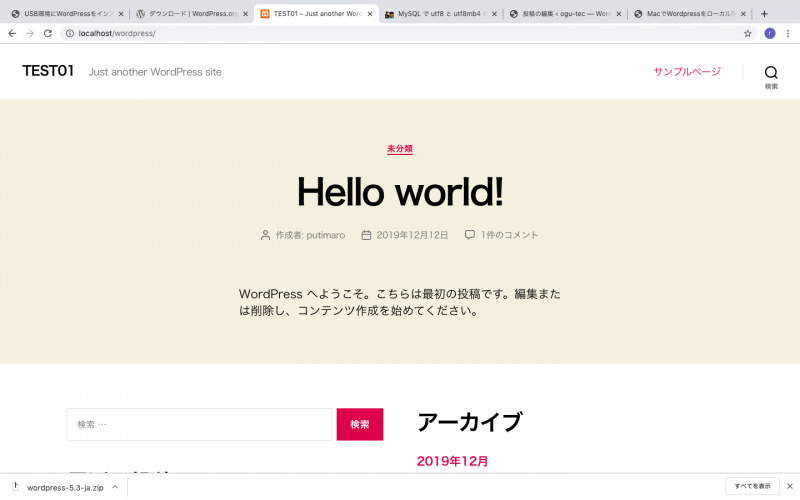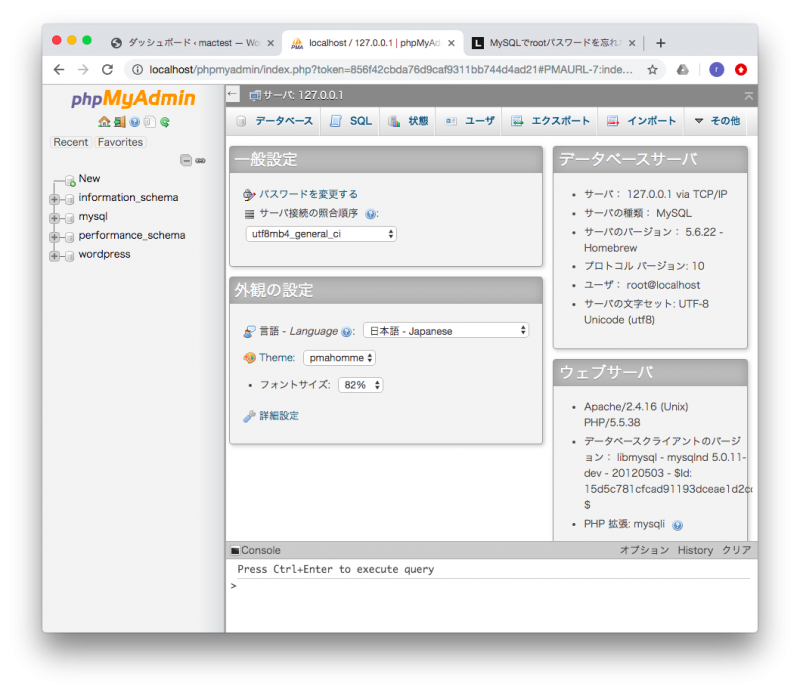久しぶりにこの話題が上ったので、やってみたところうまくいかなかった。そこでもう一度イチからやり直すことにした。その顛末。
4年前のファイルで実行してみる。環境はWIN7/64ビット版。
apacheが起動しない。お話にならない。これについていろいろと調べる。結構この症状はあるようでネットに報告されている。そのほとんどがportのバッティングが怪しいということになっていて、Skypeが槍玉にあがっていた。しかし、小生の環境には当てはまらない。
そこでイチからやり直す。
Xampp環境の構築
これがないとWordPressをローカルで開発できない。他でもいいのだが、要するにローカルサーバー環境を作るに手っ取り早いのがこのXamppだ。これでapache、Mysql、PHPを導入してローカルサーバー環境を作るわけだ。しかもUSBに。(あらかじめ空のUSBメモリー(5Gもあれば充分)を用意し、PCに接続してドライブレターを確認しておくとよい。)
Xampp最新版の入手
SOURCEFORGE > XAMPP Windows > 7.3.11 と辿って
xampp-portable-windows-x64-7.3.11-0-VC15.zip
をダウンロード。(いくつかあるが解凍ソフトがいらないzip版がいい)
Xampp最新版をUSBに展開
xampp-portable-windows-x64-7.3.11-0-VC15.zipを右クリックして「展開」を選び。
展開先にUSBのドライブレターを入力し、展開。
(あらかじめ空のUSBメモリーを用意し、PCに接続してドライブレターを確認しておくとよい)
Xampp-control.exeを実行して動作確認
USBの中にあるxamppフォルダ内の
Xampp-control.exeを実行(うるさいことは無視)
Apache Startボタンを押す
エラーが出ないことを確認し、
ブラウザを立ち上げ、http://localhost/ と入力(Apache Adminボタンを押しても同じ)
何かしらの表示が出ればOK。
apacheが動いていて、ローカルWEBサーバーとして機能しているということだ。
MySQL Startボタンを押す
エラーが出ないことを確認し、
ブラウザを立ち上げ、http://localhost/phpmyadmin/ と入力(MySQL Adminボタンを押しても同じ)
サーバ:127.0.0.1が立ち上がっていればOK
MySQLが動いていて、データベースが機能しているということだ。
(ここでトラブル発生。なんとUSBが外れてしまった。これはいけない。もう一度さしなおして同じことをやったがエラーが出て実行できない。これは正式な終了がなかったためである。そこで「タクスマネージャ」を起動して、ApacheとMySQLを終了させなければならない。こうすればもう一度起動できる。これはUSBならではのトラブルなので銘記しておく。)
その他設定
パスワードの設定
http://localhost/phpmyadmin/ で
ユーザーアカウント
root localhost ……… [特権を編集]をクリック
上部にある「パスワードを変更する」をクリック
2度書いたら右の「実行」をクリック
(この情報は必ずメモしておくこと)
再度
http://localhost/phpmyadmin/ にアクセス
エラーがでたら、
テキストエディターで xampp>phpMyAdmin>config.inc.phpを開き、
以下のように編集する。
/* Authentication type and info */
$cfg[‘Servers’][$i][‘auth_type’] = ‘cookie’;
$cfg[‘Servers’][$i][‘user’] = ”;
$cfg[‘Servers’][$i][‘password’] = ‘設定したパスワード’;
$cfg[‘Servers’][$i][‘extension’] = ‘mysqli’;
$cfg[‘Servers’][$i][‘AllowNoPassword’] = true;
$cfg[‘Lang’] = ”;
上書き保存し、
再度
http://localhost/phpmyadmin/ にアクセスする。パスワードを聞いてくるはず。
その他の設定(php.ini)
テキストエディターで xampp>php>php.iniを開き、
時計合わせ
「date.timezone=Europe/Berlin」
↓
「date.timezone=Asia/Tokyo」
に変更。
mbstringの有効化
「mbstring.language = Japanese」の先頭の「;」を削除
「mbstring.internal_encoding =」の続きに「UTF-8」を指定。こちらも先頭の「;」を削除。
編集出来たら、上書き保存。
これでXampp環境の構築はできた。USBがいわばローカルサーバとなった。
あとはWordPressの構築だ。
(ここまで詳細は
https://www.aura-office.co.jp/blog/xampp-portable/と
“https://bazubu.com/xampp-wordpress-23795.html”
を参考にしました。)
WordPressの構築
データベースの作成
http://localhost/phpmyadmin/ にアクセスする。
「データベース」タブをクリック
任意のデータベース名を入力して、「作成」をクリック
データベース名はわかりやすい任意の英数字を入力しよう。ここでは「wp-01」というデータベースを作成
照合順序は、「utf8_general_ci」を選択
WordPressの導入
WordPressのダウンロード
WordPress をダウンロードする
WordPress の日本語公式サイトにアクセスし、右上の「WordPressを入手する」をクリック。
WordPress5.3をダウンロードをクリック
WordPressのインストール
wordpress-5.3-ja.zipを展開
展開してできたwordpressというフォルダをxamppの中のhtdocsにコピーする。
WordPressの初期設定
http://localhost/wordpress/ にアクセスする。
次の画面に移ったら「さあ、始めましょう!」をクリックしよう。
データベース名「wp-01」
ユーザー名 root
パスワード、セキュリティで設定を行った phpMyAdmin にログインするパスワードを入力
ホスト名は、「localhost」
テーブル接頭辞 デフォルトの「wp_」のまま
入力が完了したら「送信」をクリック
続いて次の画面が表示されたら「インストール実行」をクリックする。
WordPressサイトの設定
サイト名 任意ブログサイトの名前になる
ユーザー名 管理画面の管理者の名前
パスワード そのパスワード
メールアドレス サイト管理者のメルアド
プライバシー チェックをはずすとよい
(この情報は必ずメモしておくこと)
入力が完了したら「WordPress をインストール」をクリックする。
「成功しました!」と画面が表示されたら「ログイン」できるか確認する。
先ほど入力した情報を入れて「ログイン」をクリックする。
ワードプレスの管理画面が登場するはず。これからはワードプレスの世界
これからこの環境でWordPressを開発する手順
- USBをPCに指す
- USB:xampp/xampp-control.exeを実行
- apache,Mysqlをスタート
- ブラウザでhttp://localhost/wordpress/にアクセス
- WordPressのユーザー名パスワードを入力してログイン
- ワードプレスの管理画面で種々の設定をする
- 記事を書いたりする
- 終了するにはまずログアウトする
- apache,Mysqlをストップする
- xampp-control.exeを終了quitする
- USBを安全にはずす
こうしたことを繰り返してwordpressを勉強してください。
以上