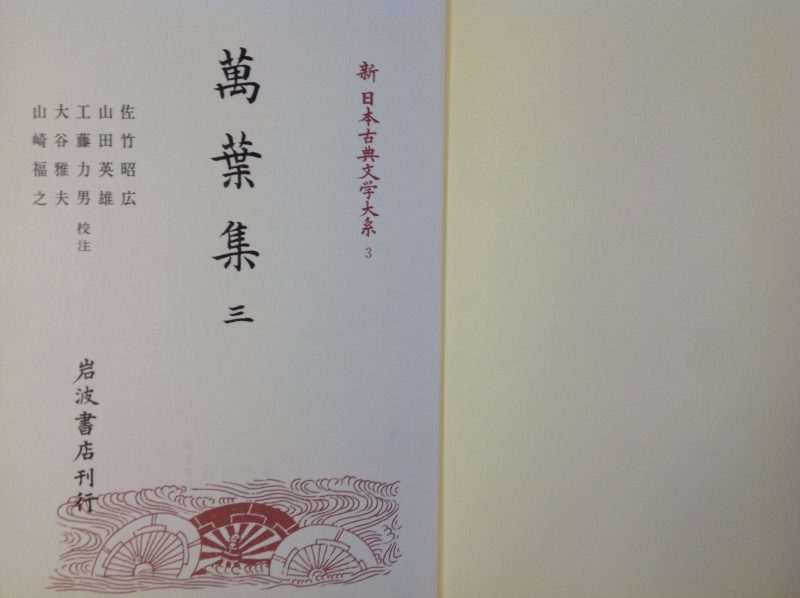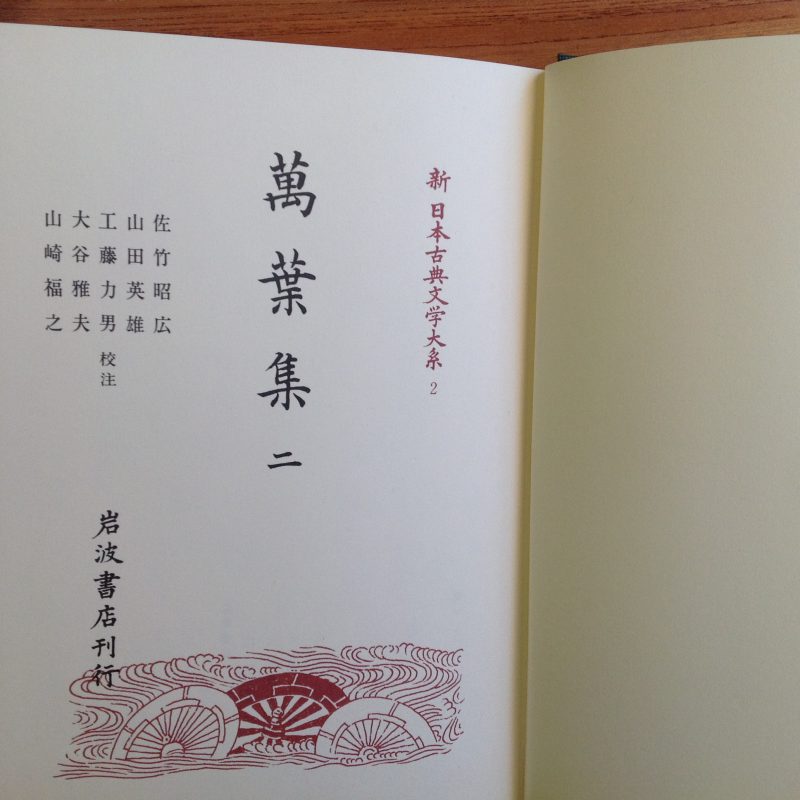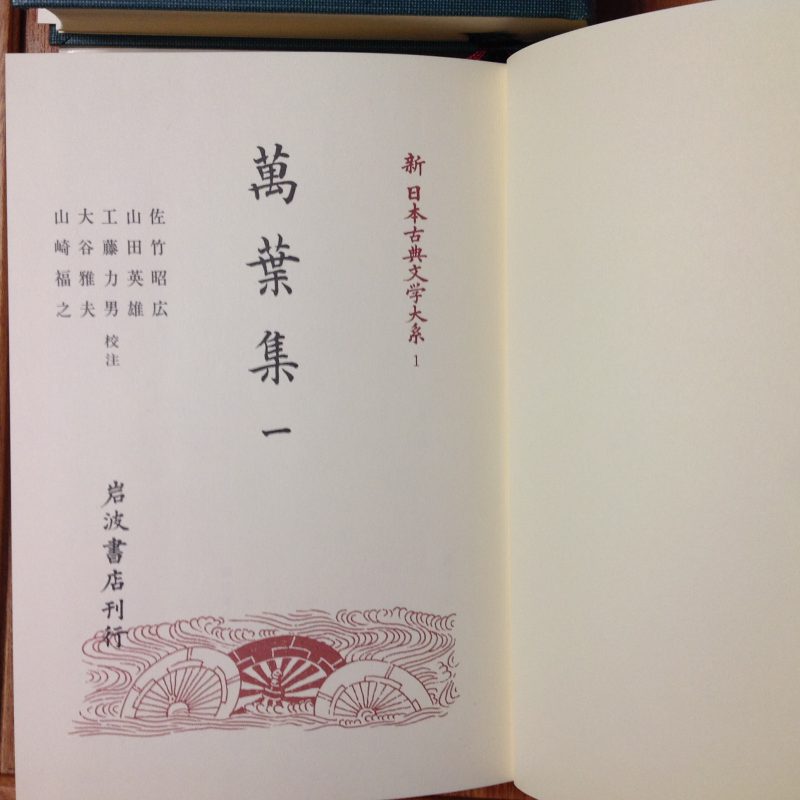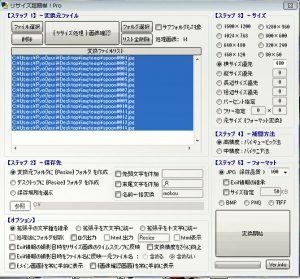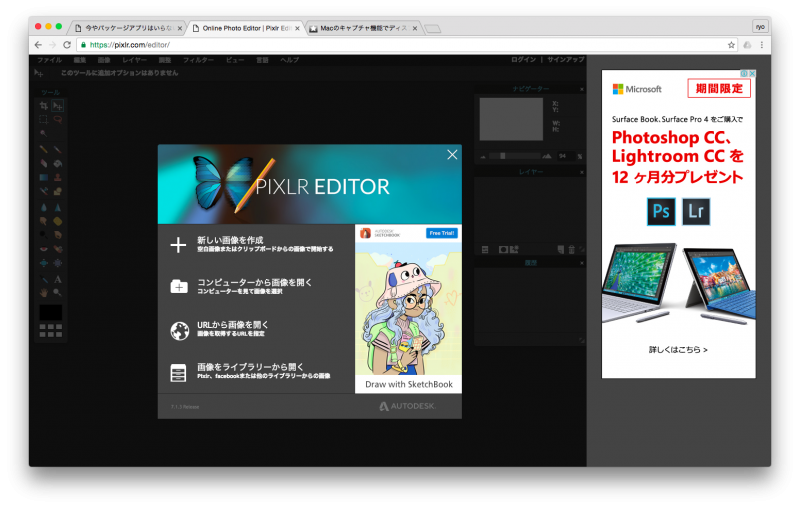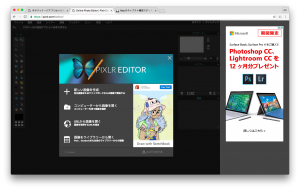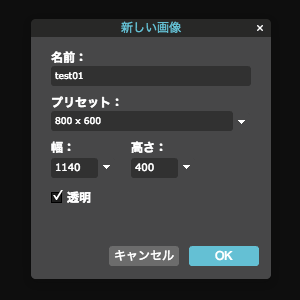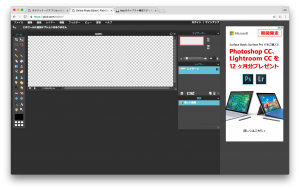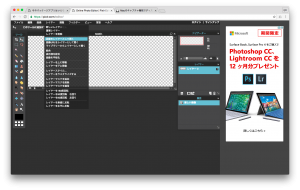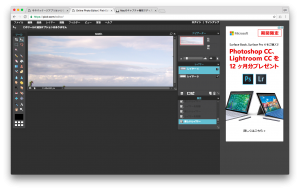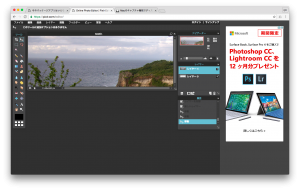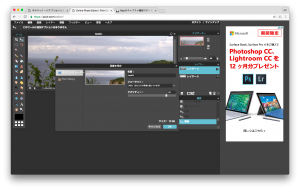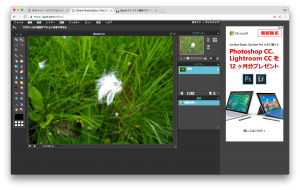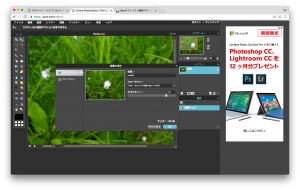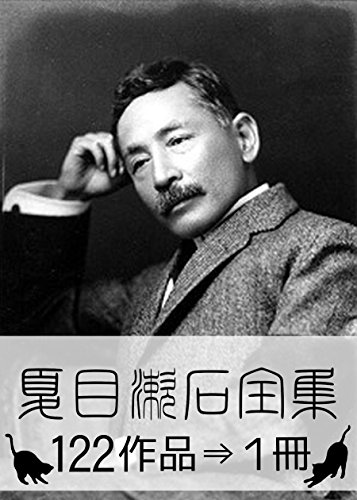『萬葉集』を読む2の1
3冊めには以下の歌が収まっている。
巻11
旋頭歌2351から2367
正述心緒2368から2414・2517から2618
寄物陳思2308から2414・2619から2807
問答歌2508から2516・2808から2827
譬喩歌2828から2840
巻12
正述心緒2848から2850・2864から2963
寄物陳思2851から2863・2964から3100
問答歌3101から3126・3211から3220
羈旅発思3127から3179
悲別歌3180から3210
巻13
雑歌3221から3247
相聞3248から3304
問答歌3305から3322
譬喩歌3323
挽歌3324から3347
巻14
東歌3348から3577
巻15
新羅国に派遣された使人の歌3578から3722
中臣宅守と狭野弟上娘子との贈答歌3723から3785
巻十一
ここはちょっと変わった配列になっている。歌体や表現法で分類している。ここからはほとんどが読み人知らずの歌だ。
最初に現れる旋頭歌はその後ほとんど姿を消す歌の形式で五七七を2回繰り返した6句からなる形式。上三句と下三句とで詠み手の立場がことなる歌が多く、頭句(第一句)を再び旋(めぐ)らすことから、旋頭歌と呼ばれる。五七七の片歌を2人で唱和または問答したことから発生したと考えられている。
玉垂の小簾のすけきに入り通ひ来ねたらちねの母が問はさば風と申さむ
と言った歌がある。
正述心緒には当時信じられていた衣の紐に関する迷信の歌がある。
君に恋ひうらぶれ居れば悔しくも我が下紐の結ふ手いたづらに
故もなく我が下紐を解けしめて人にな知らせ直に逢ふまでに
衣の紐が解けるのは思い人が思っているからだとする伝説というか迷信、なかなか面白い。
寄物陳思からは
水底に生ふる玉藻のうち靡き心は寄りて恋ふるこのころ
問答歌からは
鳴る神の少し響みてさし曇り雨も降らぬか君を留めむ
鳴る神の少し響みて降らずとも我は留まらむ妹し留めば
を引いておこう。
巻十二
この巻の初めに「古今相聞往来歌類之下」とあり、前の巻十一と同じような構成になっていることから巻十一はその「上」となるのかもしれない。
ここでは上にない羈旅発思の歌と悲別歌から引く。
我妹子し我を偲ふらし草枕旅のまろ寝に下紐解けぬ
草枕旅の衣の紐解けて思ほゆるかもこの年ころは
草枕旅の紐解く家の妹し我を待ちかねて嘆かふらしも
ここも「紐」の歌。
息の緒に我が思ふ君は鶏が鳴く東の坂を今日か越ゆらむ
巻十三
この巻は従来の分類に戻っている。しかし、収められている歌が長歌と返歌のセットがほとんどだ。ここも読み人知らずの歌がほとんどだが、古い歌が多いように思う。
蜻蛉島大和の国は神からと言挙げせぬ国…….(長歌)
大船の思ひ頼める君ゆゑに尽す心は惜しけくもなし
歌は恋い焦がれる思いを直接に高らかに歌っている。ここに萬葉集の大きな特色があると言える。これは次の東歌にも言えることなので次の巻でもふれる。
巻十四
東歌は文字通り東国の歌だが、東国の範囲は信濃すなわち長野県や遠江すなわち現在の静岡県を西の端にしてそれより東の国ということになっている。国別及び歌の内容ごとに歌を並べて、最後に「未だ国を勘へざる」とした歌を収めている。
東歌はどのように収集したのだろうか、興味深いところだが、歌われている場所が限られている傾向があって、後の歌枕的な場所がこのころから定まっていたようにも思える。また、萬葉集編纂時にはすでに風土記ほか地方の国々の様子を報告する文書があったように思われ、都人によって選択された歌であったには違いない。ただ、東歌独特の語彙や語法も見られる点は興味深く、内容も身近な恋愛感情を歌った歌が多いのも特徴だ。
まずは相模の国から引く。足柄山の歌が多いので。
足柄のをてもこのもにさすわなのかなるましづみ子ろ我れ紐解く
ちょっとスリリングな男女の密会を歌っている。
有名な東歌
稲つけばかかる我が手を今夜もか殿の若子が取りて嘆かむ
これも男女の歌。
前にも触れたが、東歌にもこうした男女の恋愛感情、というより恋愛そのものを歌った歌が多く、ここがやはり日本古代の歌の特徴であり伝統と言える。要するに平和主義者が昔から多い国なんです。
巻十五
この巻は少し変わっていることは初めに触れた。すなわち「新羅国に派遣された使人の歌」と中臣宅守と狭野弟上娘子との贈答歌が収められている。主に九州の防衛にあたった防人の歌は有名だが、こうした歌もあるのが面白い。
幾つか引いてみる。
遣新羅使(けんしらぎし)の壬生宇太麻呂(みぶのうだまろ)の歌。妻(恋人)を思う歌
旅にあれど夜は火灯し居る我れを闇にや妹が恋ひつつあるらむ
新羅に遣わされた人たちの内のひとり、雪宅麻呂が壱岐の島で病気のために亡くなり、葛井子老(ふじゐのむらじおゆ)が彼の死を悼んで詠んだ歌。
黄葉の散りなむ山に宿りぬる君を待つらむ人し悲しも
中臣宅守と狭野弟上娘子の贈答歌には中臣宅守が罪を犯して配流された事件が背景にあるようで、事情は詳らかではないが、ここにその時の贈答歌が収められているのが面白い。こうした歌に注目する編者の目が面白いと思うのだ。
二人の歌を引く
狭野弟上娘子の歌
君が行く道の長手を繰り畳ね焼き滅ぼさむ天の火もがも
強烈な歌である。
それに対し中臣宅守の歌のなんと穏当なこと。
あをによし奈良の大道は行きよけどこの山道は行き悪しかりけり
この項了