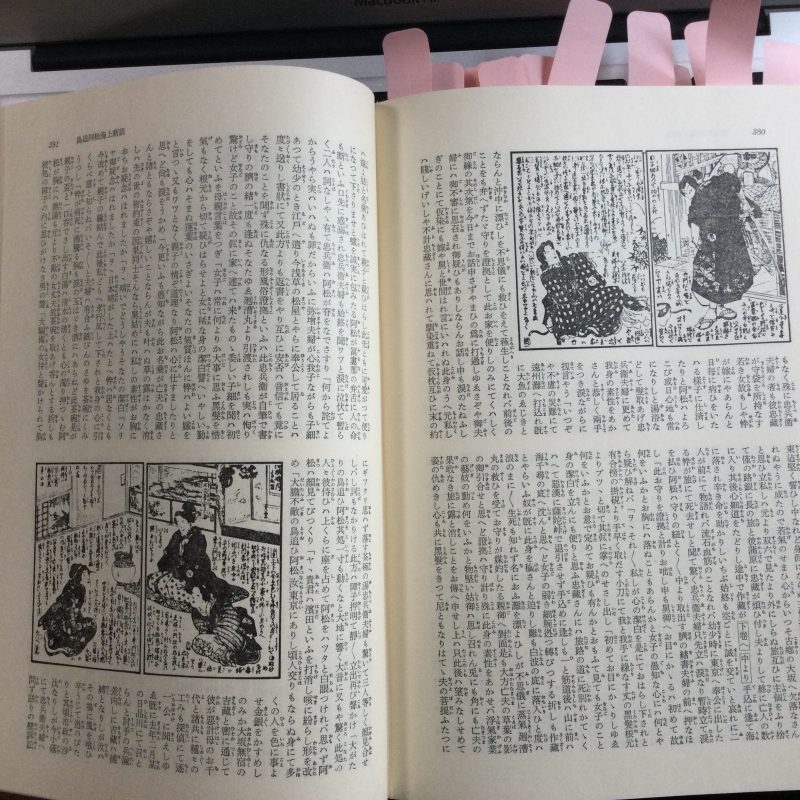Contents
はじめに
先月日本古典文学総復習正続終了したので、今月からは『明治文学全集』100冊(正確には99冊)の読破を始める。しかし、いきなり戸惑った。近代とはいえ、明治初期の作品は実に読みにくい。というのは表記や表現は古典同様というか、古典以上にわかりにくいのだ。しかも、この全集には古典作品によくある頭注が全くない。それに二段組で活字が小さいときている。(また総ルビなので余計に読み難い)極めて読むのに難儀した。しかしそんなことばかりは言ってはいられない。ともかくなんとか以下の作品を読んだので、その読みを記していく。
假名垣魯文の作品
「萬國航海西洋道中膝栗毛」
まずはこの作品。題名だけは聞いたことがあるという方は多いと思う。明治初期の作品には必ず次の「安愚樂鍋」とともに挙げられる作品だ。まずはその凡例を引く。
凡例
元祖十返舎一九が作なる道中膝栗毛の初編刊行なりて世に流布せしは享和二年壬戌歳の春にして當年を去ること既に六十九年に及べり。(中略)僕年来戯作の筆に口を糊せど滑稽の道に疎く笑語頗る不可にして斯かる稗史を綴らんこと世の嘲りを招くに似たれど活計を如何せん。趣向新奇を競ひ標目未発を可なりとするがゆゑに弥次北八の三世の孫等外国廻りの滑稽をもてこの稗史の大意とす(中略)さもあらばやつがれが文盲なる書は草冊子の外を読ず何ぞ学ばん異邦の事情、然れども文物盛典の徳たる近世福沢先生を始め諸々の洋学先生が著述されし翻訳の書とぼしからねば其階梯にとりつきて大略お茶を濁すものなり(下略)(一部漢字を現代表記等に書き換え。以下同)
これを読めばこの作品の概略はわかるはずだ。いわゆる弥次喜多道中記の近代版というか海外旅行版というわけだ。しかしここで断っているように作者は海外など行ってはいない。その頃盛んに紹介された海外事情の著作を利用している。また実際に洋行した人物に話を聞いたという。
作品は初編上下からなんと一五編下まで30巻に及んでいる。多分よく売れて読まれたのだと思う。内容は主人公弥次喜多が大商人の手代としてロンドンの博覧会見物に行くことになり、上海、香港、シンガポール、マラッカ、スマトラ、セイロン、アデン、スエズ、カイロ、マルタ島、ジブラルタルをへてロンドンに着く。そして一気に横浜まで戻るところで終わっている。こう書くと随分と現地の風物が描かれていると思うし、なかなかの紀行文学というふうになりそうだ。しかし、内容は全く異なる。要するに滑稽本そのままなのだ。江戸時代の戯作の滑稽本の舞台が洋行になっただけの話である。実にナンセンスのオンパレードなのだ。例によって女郎屋の話や下ネタ、ふざけた失敗談が中心だ。
例えばこんな下りがある。
波羅門の糞としらぬが佛國
喰ひしあとの口をしきかな
弥次郎ハこれを聞くより例の口から出たらめに
佛とひる法屁の玉のまろめ菓子
くさいものとハしらずに喰
通次郎もしばしかんがへ
きたなしとしらで喰ひたる尻割ハ
大小便の通辞役なり
(五編下)
またこんな調子だ。
ちゑ舌もまハってくるハまわってきたハ。エー。ビー。スイー。デイー。イー。清濁の二ツの唇の軽重開口さハやかに。エフ。ジー。エイツチ。アイ。ゼイ。ケイ。エル。エム。エン。オー。いつぴんあいたいやアわんろ。一ろくどんたくちゑはうす。のみかけこっぷにどろんけん。あちやさんのちゃんちゃん坊主。南京米のなまがみ。天竺米のなまがみ。パン小麦のパンなまがみ。椅子エイス。数種異人。砂も貨幣ドル貨幣。紙ちょ幣にドル貨幣。どるくわへいの紙ちよへい。紙ちよへい。どるくわへい。ぷろいすのぷりてすたんと。あめりかのかりほるにや。(後略)(十編下)
こうした表現に当時の読者は慣れていたのかと思う。しかし、今やこうした表現は謎解き以外の何者でもないように思ってしまう。
「牛店雜談安愚樂鍋」
これも假名垣魯文による滑稽本。江戸時代の式亭三馬による『浮世風呂』の銭湯、『浮世床』の髪結床に代えて、明治初期に人気となった牛鍋店を舞台に、そこに集るさまざまな客の風態や会話を描いた作品。場所が限定されているだけに当時の風俗、人物が前作よりよく描かれているように思う。
初編二篇に以下の人物たちを登場させている。
◯西洋好の聴取 ◯堕落個の廓話 ◯鄙武士の独杯 ◯野幇間のおべっか ◯諸工人の侠言
◯生文人の会談 ◯商個の胸会計 ◯薮医の不養生 ◯文盲の無茶論 ◯半可の浮世談
◯人車の引力言 ◯話家の楽屋落
一つだけ引く
◯西洋好の聴取
▲年ごろハ三十四五の男いろあさぐろけれどシヤボンをあさゆふつかふと見えてあくぬけていろつやよくあたまハなでつけかそうはつにでもなるところが百日このかたはやしたるを右のかたへなでつけもつともヲーデコロリといへる香水をつかふとみえてかみのけつやよくわげハかくべつおほきからずきぬごろのみちゆきぶりに……(後略)「モシあなたエ牛ハ至極高美でごすネ此肉がひらけちやアぼたんや紅葉ハくへやせんこんな清潔なものをなぜいままで喰ハなかったのでごウせう(中略)肉食をすりやア神仏へ手が合されねへのヤレ穢れるのとわからねへ野暮をいふのハ究理学を弁へねへからのことでげスそんな夷に福澤の著た肉食の説でも読せてへネ(後略)」
いかにも新しずきのキザな男を登場させている。今でもこういう人物いるのではないかな。これも新時代の風俗なのだろう。
「河童相傳胡瓜遣」
これは福沢諭吉の物理学書「窮理図解」のもじり。内容は全く「窮理」とも「胡瓜」とも関係ない。
凡例に
一 此小冊子翻訳書の表題を假用して号くれども更に翻訳の躰載に倣ハず専ら通俗の語を用ひ滑稽諧謔を旨として理屈に拘ハらざるハ窮理を胡瓜と付会たるを看て知るべし但し其事河童より伝習なれバなり
一 目次ハ湿気の章は運気の事とし空気の章を食気の事とし水の章風の章ハ矢張其の儘に原目を假用せる類あり不知其事に臨みて筆頭思ひ出る随意の趣向を設く則ち戯述の戯述たる故縁なり
とあるように福沢諭吉の物理学書「窮理図解」の章立に沿って、
第一章「湿気」を「運気」として「開運の身の上話」を、
第二章「空気」を「食気」として「下卑の食乱」を、
第三章「水」はそのまま「水」だが「酔狂の放心」を
第四章「風」はそのまま「風」だが「柳橋の春風」を
第五章「雲と雨」は「雲雨」として「遊女の通路」を
語るという趣向だ。
例によって内容はほとんどナンセンスだが、第二章の「食気」に登場する書生が翻訳のバイト代でやたら食い気を満たす話がこれも開化の風俗らしい。
「大洋新話蛸入道魚説教」
海底の竜王が地上の社会改革の話を聞き、海底の生物たちにも「文明と啓蒙」を促進する同様のプログラムを採用するよう命じるという話。
本文の一部
殊更南に太平洋西に大西洋の二大海あり其海底の各龍王疾くも人界の開化を聞知り各龍洲に固陋を改め海化に進む時に至り我浮漂洲のみ安閑と海中に孤立せバ版図忽地隣に併合られなんこと必せり
本文の末尾
逐一決定建白仕まつらんと漢語尽しでこむつかしく尾鰭を張て演かけたり
この作品は冒頭から漢文調で滑稽本にはない硬い表現。初編の二回で終わっているのはあまり評判が良くなかったからのようだ。文明開化を説くというところだけに趣旨があって、それを海中にも求めているというところに魯文らしい発想はあるのだけれど、ちょっと表現が生硬過ぎた感じだ。
假名垣魯文の作品はここまで。
万亭応賀篇の作品
「當世利口女」
今度は万亭応賀という戯作者の文章。この人物假名垣魯文とは随分と異なる。魯文は新時代の風俗を面白おかしく語ったが、この応賀は全面否定という感じだ。
まずはこの「當世利口女」は福沢諭吉の「かたは娘」という文章への真っ向批判だ。福沢は女性の眉毛剃りとお歯黒を自ら「かたわ」にしているようなものだと語った。
冒頭に言う。
眉毛そる我を笑へばわれハまた
耳鐶と顔の網をわらふぞ
末尾には
私として国の風俗を悖り世上の普通に異なる者あらバ渠こそ反て吾国のかたわものとわれハ思ふぞ穴賢
と結んでいる。
要するに風俗にはそれぞれの国の特徴があって、それを全面否定してはならないとしている。
「分限正札智惠秤」
「それ智者は、万事ばんじ転ばぬ前さきに杖をつけば、悔やむこと稀なり。」と言い。無闇に西洋かぶれの知識では決してうまくはいかないとしている。例えば以下のように語る。
愚人にも身の頭痛を以て一二日先の雪や雷鳴をしるものあれども究理発明の看板を掛ながら悪風暴風の兆もしらずに人命を魚腹に葬り大金の荷物を海に捨る舩ままあるを聞が。是等は究理尻の尻しらずと吾は思へり
ちょっと牽引附会の誹りを免れないが、福沢の「究理」が嫌いなのだ。
「青楼半化通」
本文
修行のために東京に来り或学校に入て間もなきに此猫又の片より開化屋といふ娼家におもむき流石野といふ娼妓に馴染て必用の洋書までを売払ひて修行に怠りければ終に学校を放逐されて本国に立ち帰りしが(後略)
今般家禄奉還の金貨を請取ゆへ是を以て一廉の商方に就名を天下に輝すにハ当地に限るものなれバ後月出府に及びけるが迚も洋学のベロベロにては埒があかねバ(後略)
と言うことで、洋学を学ぶために上京した田舎の武家の息子が学問に専念する代わりに、吉原の遊郭に出入りするようになり、一旦は金を失い田舎に帰るが、家禄奉還の金を得て花魁のパトロンになった。歓楽街の権威として出世した。西洋の学問なしにだ。こうして応賀は、西洋の学問の力だけが出世をもたらすという福沢の主張をあざ笑ったようだ。
「近世惘蝦蟇」
「きんせいあきれかえる」と読む。小冊子。冒頭に
唐土の痩蝦蟇は
仙人に駆使せらるれど
日本の此蟇はは我慢仙人を
駆使して世中を惘かへると笑ふ
世人此蟇にかならず
笑ハれること
なきを欲せよ
とあり、これも文明開化に否定的な主張を表したもの。
しかしそれにしても魯文の文章より、まして読みにくい文章だった。
梅亭金鵞篇「寄笑新聞」
第一号から第一一語までの新聞というよりは雑誌。これもやや反時代的な内容。士族の現状を語ることが多いように思う。「笑い」はほとんどない。内容は実は商業的なものだ。
第一号は「金貨大評議」二号は「金借手前目算」三号は「貸借問答」という内容だ。これは金を巡る話。特にこの時代の士族の有様を描いている。一一号の「士商論」にそれははっきり表れている。この士族の現状を語るスタンスは自ずから近代化の風潮への批判となる。七号の「のぞき眼鏡欧行論」は外国留学、洋行流行を批判しているし、十号の「学問のすずめ」はもちろん福沢諭吉等洋学者を風刺した内容だ。
しかし、実はこの梅亭金鵞はこの「寄笑新聞」を別名で発行している。この梅亭金鵞の名で啓蒙書籍も出版していたようだ。この一見矛盾した姿勢にこの時期の知識人の一つの姿があるようだ。
條野採菊・染崎延房篇「近世紀聞(抄)」
全十一編あるという。黒船来航から西南戦争に至るまでを記した所謂通俗的な近世史ということになる。ここは以下の第四編までを収める。
第一編
亜船初めて浦賀へ着する事
亜国の書簡を和訳し各藩に示さる
墨使再び来舶及び各国通商を請ふ
朝議厳にして幕吏鎖開の間に困む事
五カ国互市の条約を結ぶ事
桜田の上巳に紅雪を降す事第二編
浪徒蜂起して薩長大に周旋ある事
永井が入説調わず遂に勅使東下する事
島田梟首並関東大変革の事
列藩次第に入洛して京師繁栄の話
尊攘決議して鴨男山へ行幸
長海に五回外国船を砲撃す第三編
薩海戦争及び大樹東下の事
一橋殿問答及び洛中動揺
朝議一変して七卿長門へ下向の事
県令を誅して浪士等五条に拠る事
山嶽に立籠りて天誅組四藩と戦う第四編
南山の義挙鎮静する事
平野憤激して沢卿を誘ふ
生野銀山に義党等屯集する
但州鎮静及び長の両士入洛を請ふ
将軍家上洛 宸翰を賜る事
筑波太平の両山に有志ら屯集の事
内容はこれでわかるが、史実、巷説、風説の全てが盛り込まれているという。以後大衆作家の種本となったという。
松村春輔篇「開明小説春雨文庫」
第六編の「敍」に
男女同権てふことを唱へ出せるハ、西洋風の伝染にして、耶蘇者流より出づるものならん。茲に掲ぐるは同権を同賢となし、男子と並べて近世の義女貞女孝女の類ひを挙て、春雨文庫の宝物となさんとし、既に第六編に至りたり。
とあるようにこの作品は当時、幕末から明治初期にかけての「義女貞女孝女」と言った女性を描いた短編小説をシリーズ化したものということになる。
その第一編にある以下の句は貧しさ故に親のため苦界に身を売られた女がアメリカ人には身を委ねることができずに自ら死を選んだという話の句。
露をだにいとふ倭の女郎花
ふるあめりかに袖ハぬらさじ
ここには如何にも旧時代の孝女を描いているように思われるが、一方筆者は以下のように語り、
引続き節婦孝女の物がたりにて近世稀なる真面目を表し頗る珍説を探り併ハせて序次に大部に逮ぶ最も目出度き春雨文庫は人情本の部類ならずして自然に人情の極意を知り交際事に迂遠人でも此文庫を開き給へば随つて愛国の志しに進み臆守るべからざるものハ旧習なりと(後略)
必ずしも旧習を重じているわけではないとしている。こんなところにもこの時代の特徴が窺える。
久保田彦作篇「鳥追阿松海上新話」
初め仮名垣魯文の『假名読新聞』に明治10年12月10日からつづき物として連載されたという。後にあらためて単行本として刊行されたという。内容は所謂「毒婦物」ということになる。「春雨文庫」とはかなりテーストが異なる。明治の新時代を背景にいわば懸命に生きた「悪女」の物語だ。
鳥追とは江戸時代に家々を回って三味線を弾き語り、鳥追い歌を歌う門付芸人の女性のことだが、身分は最下層の「非人」だ。もちろん貧しい生活を強いられて育ったはずだ。しかし、その美貌を武器に多くの男たちをたぶらかし、全国をまたにかけて生きてゆく。その中でも政府の要人となった男との出会いとその関わりが大きな筋となって話が展開してゆく。ここに新時代で出世し横暴に振舞う男をその色香でたぶらかし破滅に追いやろうとする主人公の姿が庶民に受けたのかもしれない。しかし、最後は落ちぶれ、かつて騙した男にお恵みをもらって生きたが、終に不遇のまま死んでしまうことになる。
現代でも週刊誌ネタとして「悪女」の話は結構受ける。少なくとも「孝女」「貞女」の話よりは庶民は好きなのだ。この時代においてもそうだったらしく、こうした「毒婦」物は以後も書かれてゆく。
終わりに
なんとか一回目を終えることができた。前にも書いたと思うが、この小生の仕事は「締切」があるわけではないので急ぐ必要はないのだが、実は人生の「締切」も迫っているのも確かだ。一ヶ月に1冊では八年以上かかってしまうことになる。ま、特にこの明治初期の作品が読み難いということをもって仕方がないということで、徐々にいくしかないとは思っている。次回は明治開化期文学集(二)ということになる。
この項 了
2025.04.23