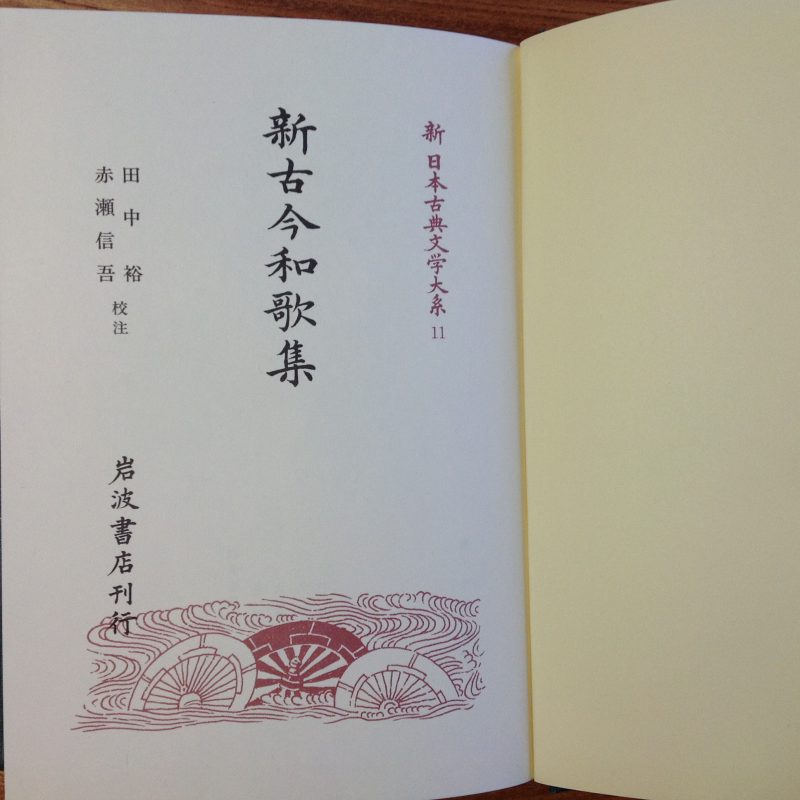『新古今和歌集』を読む
ここで、いわゆる八代集の最後『新古今和歌集』を取り上げる。この「新日本古典文学大系」は「萬葉集」から始まって、この『新古今和歌集』まで、歌集を並べている。これは和歌集が日本古典文学においてしめた役割の大きさから言って当然だが、この『新古今和歌集』で一応の終わりを示しているのも意味があると言える。この歌集はいわば和歌の時代の終わりを告げていると言ってもいい歌集だからだ。
古今集以来続いた勅撰集の歴史もこの後続くには続くが、この「新古今」で一つの達成?というより「行くところまで行ってしまった」感があるからだ。その後韻文の中心は連歌や俳諧に譲ることになる。
さて、この新古今は鎌倉時代の初頭に成立している。これは社会が平安の貴族中心から関東の武士の時代へと移り変わっていく過渡期に成立したと言うことだ。この勅宣をしたのが、後鳥羽天皇であったこともその歌集の性格に影響していると思える。周知のように後鳥羽天皇は平家が滅亡した後に即位した天皇である。また、その当時成立した鎌倉幕府に反旗を翻したことでも知られている。つまりこの歌集は滅びゆく貴族社会の最後のあがきを示しているとも言える気がする。
では、実際にどんな歌が収められているのだろうか?
この『新古今和歌集』には約2000首の歌があるが、その内訳は萬葉からが100首足らず、古今時代の歌人の歌が400首足らず、後は当代の歌人達の歌である。
形式的に一応万葉集からも再録し、古今時代の歌も取っている。(しかし、古今集以来の三代集に収録された歌は取っていない)歌人別では一番多くの歌が取られているのがなんと西行である。94首ある。これは後鳥羽院の西行好きが影響しているのだろうか?ともかく後鳥羽院のサロンに関係した歌人達の歌が多い。そのなかでこの歌集の特徴を最も鮮明に示しているのが選者の一人藤原定家である。歌数は46首と控えめだが、この定家の歌こそ良くも悪くもこの新古今の歌の特徴をよく示していると言えそうだ。そして定家の「本歌取り」という手法がこの時期の歌の本質をよく示している。
したがってここでは定家の歌を「本歌取り」という観点で見ていくことにする。
春の夜の夢のうき橋とだえして峰にわかるる横雲の空
有名な歌である。実にいい歌だと思える。ところがこの歌には本歌がある。古今の忠岑の以下の歌だ。
風吹けば峰にわかるる白雲のたえてつれなき君が心か
まず「峰にわかるる雲」が使われているのがわかる。「たえて」と「とだえして」も類似した表現だ。ただ、それだけではない。「夢のうき橋」という語も源氏物語の最終巻の題名であることもわかって使っている。さらには「春の夜の夢」という語句が平家物語にあり、定家の造語であるとは考え難い。(定家と平家物語にはつながりがあるようだ)また、「横雲の空」という語句も漢文に出典があるとも言われているようだ。こうなると、本歌取りばかりではなく、様々な古典からの借用でこの歌は成り立っていると言えるのかもしれない。
では定家のオリジナリティはどこにあるのだろうか?
それを考えるには忠岑の歌との違いを考えてみるといいかもしれない。
まず「君が心」という語があるかないかだ。忠岑の歌は結局「たえてつれなき君が心」に情景を持っていくというか、それを引き出すために情景を詠んでいると言えるが、定家の歌にはそうした詞はなく、ただ情景だけを詠んでいるように見える点だ。様々な典拠を持つ語句を並べてそこに一つの情景を作り出し、さらにその情景に仮託された情緒を描き出している。
この歌を素直に読めば、男女の朝早くの別れ(後朝の別れ)を彷彿させる。後ろ髪引かれながら女の元から帰っていく男の心情を読み取ることもできる。
ただ、この情景や情緒とて実感から引き出されたものではない。まさに和歌の世界で謂わば人工的に作られている。
もう一つ忠岑と定家の歌の違いに上の句と下の句の関係がある。忠岑の歌は上の句と下の句がひとつながりだが、定家の歌には断点がある。文法的には「して」という語で後に接続するように思えるが、下の句が体言で終わっている点から謂わば連句のような形になっている。これは私が後の俳諧に親しんでいるせいかもしれないが、上の句が俳諧の第三のようで、下の句が付句のように思われる。
こうした定家の歌の特徴は次の歌にも窺える。
さむしろや待つ夜の秋の風ふけて月をかたしく宇治の橋姫
この本歌は古今の読みひと知らずの以下の歌だ。
さむしろに衣かたしき今宵もや我を待つらむ宇治の橋姫
「さむしろ」「かたしき」「待つ」「宇治の橋姫」が使われている。しかも結句は同じである。古今の歌は「宇治の橋姫が筵にひとり寝をして今宵も私を待っているだろうか」という男の歌だ。定家は多くの言葉をこの歌から借りながら、秋の情景へと変換する。ポイントは「秋の風」と「月」だ。「秋」は「飽き」に通じる。むしろ男を待つ女の心情が歌われているといっていい。「秋風」が「すでに飽きられたことを知らせるかのように夜のふけるままにふきつのる」そんな時「月光を敷いて独り寝る」「宇治の橋姫」の心情である。ただ、ここは心情と言うより、冴え冴えとした月光に照らされる宇治の橋の情景として読むべきかもしれない。そしてそれが男を待つ女の情緒を仮託する。これもそうした意味で前にあげた歌と同様な手法だろう。そしてこの歌も上の句と下の句の断点が伺える。「て」で上の句は終わって、下の句は体言止めである。上の句はそれだけで俳諧の一句として読める気がしてならい。古今の本歌にはそれがない。
さらにもう一つ
駒とめて袖うちはらふかげもなし佐野のわたりの雪の夕暮
本歌は以下の万葉集の歌。
苦しくも降り来る雨かみわの崎狭野の渡りに家もあらなくに
萬葉の歌は雨に降られた旅人の心情を詠む。しかし定家はそれを一つの情景として詠んでいる。雨を雪に変えて。これもこれまでの例と同様。
もう一つ本歌取りの例
ひとりぬる山鳥のおのしだりおに霜をきまよふ床の月かげ
本歌は萬葉の柿本人麿の以下の歌だ。
あしひきの山鳥の尾のしだり尾のながながし夜を独りかも寝む
「山鳥の尾のしだり尾」「独りかも寝む」をいただいている。人麿の歌の場合、「あしひきの」は「山」を出す枕詞であり、「山鳥の尾のしだり尾の」までは「ながながし」を出すための序詞だ。言いたいことは下の句の「ながながし夜を独りかも寝む」にしかない。それの対して定家の歌の本意は「ひとり寝の寝床にさす月の光の白さ」をいうところに眼目があり、山鳥の尾に霜が置かれているのと見間違えるほどだとしている。
ここでも体言止めが使われている。そして歌われているのは寒々しい月の光に照らされた寝室の情景だ。人麿の歌の語句を使いながら「霜」と「月影」と言う言葉を加えて情景を描き出している。
こうして定家の歌を見ていくと、絵画的な印象が強い。思いを直接に述ぶることはせずに、ある情景を描き出す。ただ、その情景は見たものではない。謂わば古今的な世界を「本歌取り」という手法で頭の中で再構築したものと言っていいかもしれない。しかもその完成度は極めて高いものだ。
これを実感を旨とする文学観からすれば「にせもの」と言えるかもしれないが、定家という人物がやって見せたことは貴族文化の行き着く最後の場所だったのかもしれない。
今回は定家の本歌取りの歌のみを見てきた。もちろんこれで『新古今和歌集』の全てを言い尽くすことはできない。たとえば一番多く取られている西行の歌についてもその違いを中心に見ていくことが必要だったかもしれない。また、後鳥羽院についても触れておきたかった。しかし、今回はここまでにしておく。
最後にこの定家の歌に後の芭蕉の俳諧への兆しを見つけたことを付け加えておく。
これでしばらく和歌から離れることになる。
この項了