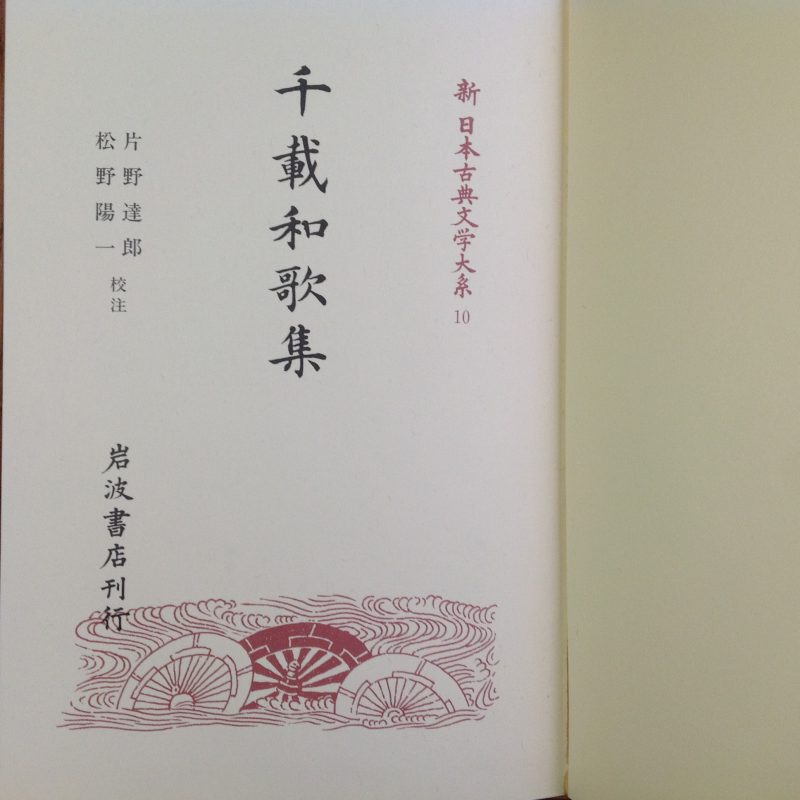『千載和歌集』を読む
歌集について
この歌集は7番目の勅撰和歌集。『新古今集』の架け橋の役割を担ったものと思われる。それ以前の『金葉集』『詞花集』がややマイナーであったのに比べると本格的な勅撰集と言える。選者は当代歌壇の中心人物、藤原俊成だ。もう一度古今集以来の伝統を再認識する意を込めて、千年の歌を集めるということでこの名がある。20巻構成も元に戻している。歌数も1288首と古今並みである。
ただ、歌は時代の変化に伴い形を変えてきている。歌の専門化が進んだといっていいか、古今以来の伝統を守りつつ技巧的になっていったと言える。そういう意味で新古今への道筋を示している。
ここでは選者の俊成の歌を見、この千載和歌集で異彩を放つ西行の歌、そしてのちに大きく取り上げられることとなる式子内親王の歌を見る。
俊成
み吉野の花のさかりをけふ見れば越の白根に春風ぞふく
春上の末尾の歌。越の白根は歌枕。現在の白山のことで、萬葉から歌に詠まれてきた。もちろん俊成はここを眺めたことはないはずだ。吉野だって行ったことがないだろう。すなわちイメージなのだ。ただ、満開の桜の吉野山を雪の白山に見立てたことがユニークなのだろう。白いイメージ。
八重葎さしこもりにし蓬生にいかでか秋のわけてきつらん
秋上にある歌。秋を人に見立てたところがポイント。草ぼうぼうの荒れた家にも秋はやってくる。人はやっては来ないんだけど、というわけか。
照射する端山が裾のした露や入るより袖はかく萎るらん
照射は「ともし」と読む。夏に山野で狩りをする時、火であたりを照射することらしい。夏の狩りの歌題。しかしここは恋の歌。恋歌一にある。
詞書きに「初恋の心をよみ侍りける」とある。それにしても初恋の心を詠むに実に凝った歌だ。狩りをする人の裾の露から袖の涙を連想するのはどうかなと思うが、様々な技巧が凝らされているようだ。「した露」は秘めた恋を暗示。「入るより」は「恋に入るより」を言う。恋の歌もここまで来てしまったかという思いがする。
おく山の岩垣沼のうきぬなは深きこひぢに何乱れけん
これも恋の歌。「ぬなは」は蓴菜のこと。ここまではいわゆる「序詞」。「深きこひぢ」を導き出すための言葉。「こひぢ」は泥や泥土をいう言葉だが、当然「恋路」をかける。また、「乱れ」が「うきぬなは」の縁語。要するに「深い恋路に迷い込んだ心」を詠んでいるのだが、ここまで技巧的になると心情は伝わらないけどね。
世の中よ道こそなけれ思ひ入る山の奥にも鹿ぞ鳴くなる
ここは率直な歌。この「世の中」は平安の男女の仲という意ではないだろう。「人生」と言ったら良いのかもしれない。この時代の貴族には新時代の胎動の仲での不安があったに違いない。「道こそなけれ」には俊成の心情が受け取れる気がする。「思ひ入る」にもそれが伺える。そして山奥の鹿の鳴き声もまたたしかに悲しげだ。こうした感情はこの集で多く仏教徒の歌が取られていることにも関係しているように思う。貴族たちにとって不安な時代だった。
西行
をしなべて花のさかりに成りにけり山のはごとにかかるしら雲
円位法師とあるが、有名な西行のこと。西行といえば「さくら」だ。桜の盛りを素直に詠む。満開の桜を白雲に見立てる。
ところで桜は現在の人間だとすぐに「染井吉野」を思い浮かべてしまうが、ここは山桜だということを改めて想像しよう。まさに山の裾に満開の山桜は白雲のようだ。
俊成はこの歌を「うるはしくたけ高く見ゆ」とした。技巧の対極にある歌い振りを評価する。
この世にて又あふまじき悲しさにすすめし人ぞ心乱れし
「哀傷歌」の末尾の歌。寂然法師の歌に対する返歌。共に修行した法師の臨終を知らせる歌に対しての歌。
「すすめし人」とは臨終正念を勧めた西行本人。臨終正念は死に際して一心に極楽往生を願って念仏を唱えること。法師にとって死は必ずしも悪いことではないはずだが、やはり会えない悲しみに心が乱れるとしている。こうした仏教的な考えはこの時代に支配的になっていったと思われる。
知らざりき雲居のよそに見し月のかげを袂に宿すべしとは
法師西行の恋の歌。「雲居のよそに見し月」は垣間見た高貴な女性の比喩。「月のかげ」は「月の光」のこと。すなわち美しいその人の面影を言うのだろう。「袂(たもと)に宿す」とは涙と共に忘れないということ。初句の「知らざりき」が我ながら思いがけなかったとしている。いい歌だ。
もの思へどもかからぬ人もあるものをあはれなりける身の契りかな
これも恋の歌。「身の契り」は自分の前世からの宿縁。苦しい恋の体験に我が身の因果を嘆く歌。これも率直な歌い振り。
仏には桜の花をたてまつれ我がのちの世を人とぶらはば
雑中にある桜の3首のうちの一つ。歌の意は解説を要しまい。有名な下の歌を思い出す。西行は桜が大好きだった。
願わくは花の下にて春死なんそのきさらぎの望月のころ
式子内親王
ながむれば思ひやるべきかたぞなき春のかぎりの夕暮の空
「ながむ」は物思いに耽る意味。「思ひやる」「思い」を「やる」こと。すなわち気を晴らすこと。要するに「春愁」。春の終わりはこうした情調を生む。深窓の内親王ならではの思いか。
神山のふもとになれしあふひ草ひきわかれても年ぞへにける
式子内親王は当時の風習に従って斎院生活を10年にわたって送った。「神山」は上賀茂神社の背後の山。「あふひ草」は「葵草」。詞書きによれば「賀茂祭の前の神事」である人が「葵草」を捧げたのをみて詠んだとある。忘れがたい斎院生活を思い出す。
草も木も秋のすゑ葉は見えゆくに月こそ色もかはらざりけれ
秋下にある歌。草木は色がどんどん変わっていくのが見えるのに、月だけ色が変わらないとしている。素直な歌い振り。
はかなしや枕さだめぬうたた寝にほのかにまよふ夢の通ひ路
恋の歌。「枕」は恋のアイテム。枕の位置で夢で会いたい人に会えるという迷信があったようだ。恋人に夢でも会えない儚さを歌う。
ふるさとをひとり別るる夕べにもをくるは月のかげとこそ聞け
「釈教歌」にある歌。「ふるさと」はここでは現世のこと。月の光だけが現世からのわかれを見送ってくれるとする。仏教的な考え方がこの頃完全に定着していたことを思わせる。
式子内親王の歌はいずれもわかりやすく素直な歌だ。
なお、平氏打倒の兵を挙げて敗死した以仁王はこの人の弟。生涯はけっして平坦なものではなかったと思われる。
テキストについてはこれまでと同じ。
この項了