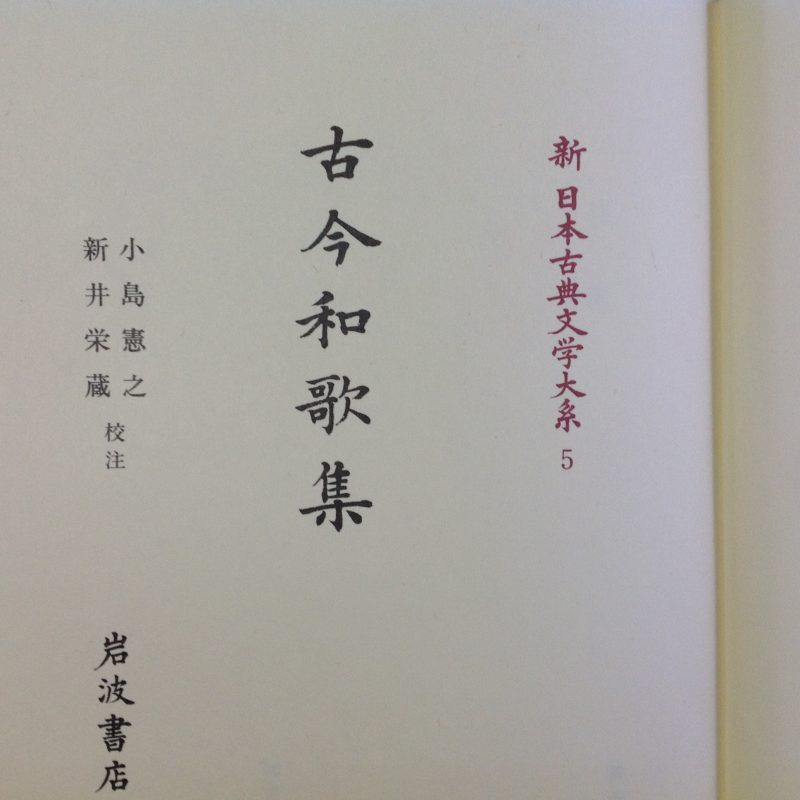『古今和歌集』を読む
この新日本古典文学大系では『萬葉集』に続くのがこの『古今集』である。そのあと勅撰集が続いているのでまずは和歌集を並べる編集方針らしい。
しかし、この古今和歌集は萬葉集とかなり違っている。改めて続けて読んでみてその大きな違いに気づかされた。
『古今和歌集』は『萬葉集』と同様巻二十ある。しかし、歌の数は1100首で萬葉の約4分の1、歌の種類もほとんどが短歌である。巻一から巻六までが四季の分類による。342首あって全体の約3分の1。また、巻十一から巻十五までが恋のうたで、360首でこれも全体の3分の1を超える。残りがその他の分類で雑歌、東歌、等である。
また、歌人の数も限定されている。詠み人知らずの歌も多いが、専門の歌人によるものが大半と言っていい。ご存知のようにこの『古今和歌集』は最初の勅撰集ということになっていることも『萬葉集』との大きな違いだ。
『萬葉集』は8世紀に成立したと考えられ、『古今和歌集』は10世紀の初頭に成立したと考えられるから違いがあって当然なのだが、ここには和歌だけではなく日本古代社会にも大きな転換点があったようだ。和文の文学史でいうと、この『萬葉集』と『古今集』との間には和歌の空白がある(現存する作品がない)のだが、その間に漢文の作品はいくつか残っている。実はこの漢文の詩文集が当時の勅撰集であった。8世紀には謂わば傍流であった和歌が社会変化にともなって10世紀初頭には表舞台にあがったということだ。
では具体的に歌を見ていこう。
春の歌
はるがすみたつを見すててゆくかりは花なきさとにすみやならへる
あだなりとなにこそたてれ桜花年にまれなる人もまちけり
けふこずはあすは雪とぞふりなましきえずはありとも花と見ましや
たれこめて春のゆくへもしらぬまにまちし桜もうつろひにけり
花の色はうつりにけりないたづらにわが身世にふるながめせしまに
かはづなくゐでの山吹ちりにけり花のさかりにあはまし物を
夏の歌
さつきまつ花橘のかをかげば昔の人の袖のかぞする
夏の夜はまだよひながらあけぬるを雲のいづこに月やどるらむ
秋の歌
このまよりもりくる月の影見れば心づくしの秋はきにけり
秋ののにおくしらつゆは玉なれやつらぬきかくるくものいとすぢ
山田もる秋のかりいほにおくつゆはいなおほせ鳥の涙なりけり
冬の歌
花の色は雪にまじりて見えずともかをだににほへ人のしるべく
こうして四季の歌をざっと読んでいると、いずれも同様な情緒、題材が並べられていてあまり面白さが感じられない。春は何と言っても桜である。萬葉にはそれほど登場しなかったように思う。鳥はウグイスだ。夏だったらホトトギス。秋は月、鹿、雁、露。冬は雪と梅。こういう題材と情緒は現代でも日本人にとって定番のアイテムだ。この定番は古今集によって作られたといっていいかもしれない。これが後何百年も日本人の和歌を支配したといっても過言ではない。
恋の歌
あさぢふのをののしの原しのぶとも人しるらめやいふ人なしに
わりなくもねてもさめてもこひしきか心をいづちやらばわすれむ
ひとしれぬわがかよひぢの関守はよひよひごとにうちもねななむ
色もなき心を人にそめしよりうつろはむとはおもほえなくに
恋の歌も古今集の大半を占めている。これは萬葉集でも言えたことで、日本人が古くから男女の関係に心血を注いできた証拠だが、古今集のそれは万葉集と大きく違っている。万葉集では男女の関係を謂わば直接的に歌う歌が多かったが、古今集のそれは「恋を恋する」と言ったらいいか、恋の情緒を楽しむといったらいいか、間接的な歌がほとんどだ。通じ合わない心を詠む歌が多いように思う。この恋の情緒もやはり日本人の恋の定番となった。
その他
風ふけばおきつ白浪たつた山よはにや君がひとりこゆらむ
こよろぎのいそたちならしいそなつむめざしぬらすなおきにをれ浪
その他の初めの歌は長いあとがきがあり、謂わば物語を背景にした歌。ちょっと萬葉ぶり。最後は東歌の一首。相模の国大磯あたりの浜を歌っている。これも古歌の雰囲気が残る。
正岡子規は古今集をこき下ろした。そして万葉集を評価した。そんな影響がこの私にあるのかもしれない。通読するとどれも同じに見えてしまうのだ。しかしもっと虚心坦懐に一首づつを切り離して時に応じて読んでみればいい歌もあるに違いない。また、この古今集が後の文学史に残した影響が計り知れないことも肝に銘じておくことも必要だろう。
なお古今集のテキストは便宜上以下のサイトから引いた。アメリカの大学のサイトだ。
http://jti.lib.virginia.edu/japanese/kokinshu/kikokin.html
この項了