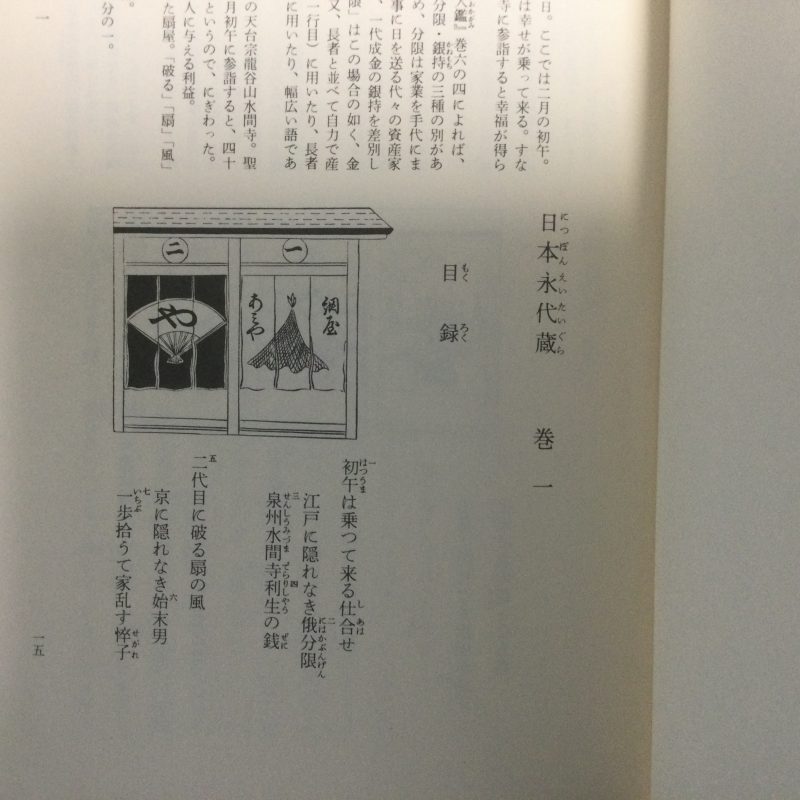はじめに
芭蕉に続いて井原西鶴を取り上げる。この古典集成には『好色一代男』『好色一代女』『日本永代蔵』『世間胸算用』の四つの作品が収められている。実はこの古典文学総復習の正編(新日本古典文学大系)で、すでに西鶴は取り上げている。それは『日本古典文学総復習』76『好色二代男・西鶴諸国ばなし・本朝二十不孝』77『武道伝来記・西鶴置土産・万の文反古・西鶴名残の友』である。ただ、ここで取り上げる作品の方がいわば代表的な作品と言える。小生もここで取り上げる作品はすでに一応目を通してきたが、ここでもう一度しっかり読んでおきたい。発表順とは異なるが、まずは「町人物」と呼ばれる『日本永代蔵』『世間胸算用』のうち『日本永代蔵』から取り上げたいと思う。
『日本永代蔵』の一般的な理解
この作品は一般的にどう紹介されているかを見ておきたい。Googleによる検索でいわばAIを使った紹介だ。以下である。
『日本永代蔵』は、井原西鶴作の浮世草子で、貞享5年(1688年)に刊行されました。町人物の代表作のひとつで、諸都市の町人の成功や失敗談が書かれた短編小説集です。
経済を中心とする町人生活を真正面からとり上げ、勤勉・節約・才知によって財産を作り、あるいは、失敗談、教訓談を織り交ぜて町人の処世法を教えます。鋭い観察とリアルな筆力とがあいまって、金と慾に生きる町人像と徳川封建社会の姿を鮮やかに描き出しています。
『日本永代蔵』は、現在の中之島界隈を舞台に描かれています。中之島を挟んで流れる堂島川と土佐堀川には諸国の蔵屋敷が並び、北浜界隈には豪商の屋敷が軒を連ね、陸は人馬が絶えず、川には無数の荷船が浮かぶ様子が描かれています。
ま、概ね間違ってはいない。しかし最後の部分は誤解を生むだろう。上段に有るように舞台は「諸都市」だからだ。もう一つは「町人の処世法を教えます」と言う部分だ。表面的には確かにそうかもしれないし、そう言う部分もあることはある。また、本を売るために今でいう「ハウツウ本」のような体裁を取る必要があったのかもしれないから、副題に「大福新長者教」とあるのもそう言える根拠となっているのかもしれない。しかしよくこの書を読めば、決してそうとばかりは言えないことがわかると思う。
『日本永代蔵』の梗概
では、その内容を見ていこう。この書は全部で6巻あり、その冒頭に一々「目録」がついていて、(「目次」のような物なのだが、)簡潔にその内容がわかるようになっている。以下である。(表記は全て「古典集成」本による。以下同)
巻一
- 初午は乗て来る仕合せ
- 江戸に隠れなき俄分限
- 泉州水間寺利生の銭
- 二代目に破る扇の風
- 京に隠れなき始末男
- 壱歩拾うて家乱す悴子
- 浪風静に神通丸
- 和泉に隠れなき商人
- 北浜に箒の神を祭る女
- 昔は掛算今は当座銀
- 江戸に隠れなき出見世
- 一寸四方も商売の種
- 世は欲の入札に仕合
- 南都に隠れなき松屋が跡式
- 後家は女の鑑となる者
巻二
- 世界の借屋大将
- 京に隠れなき工夫者
- 餅搗も沙汰なしの宿
- 怪我の冬神鳴
- 大津に隠れなき醤油屋
- 何をしても世を渡るこの浦
- 才覚を笠に着大黒
- 江戸に隠れなき小倉持
- 身過ぎの道急ぐ犬の黒焼
- 天狗は家名の風車
- 紀伊国に隠れなき鯨えびす
- 横手節の小歌の出所
- 舟人馬方鐙屋の庭
- 坂田に隠れなき亭主振り
- 明くれば春なり長持の蓋
巻三
- 煎じやう常とはかはる問薬
- 江戸に隠れなき箸削り
- 小松栄えて材木屋
- 国に移して風呂釜の大臣
- 豊後隠れなき真似の長者
- 程なく剥げる金箔の三の字
- 世は抜取の観音の眼
- 伏見に隠れなき後生嫌ひ
- 質種は菊屋が花盛り
- 高野山借銭塚の施主
- 大坂に隠れなき律義屋
- 三世相より現るる猫
- 紙子身代の破れ時
- 駿河に隠れなき花菱の紋
- 無間の鐘を聞は突き損ひ
巻四
- 祈る印の神の折敷
- 京に隠れなき桔梗染屋
- 藁人形の夢物語
- 心を畳み込む古筆屏風
- 筑前に隠れなき舟持
- 蜘の糸のかかる例も
- 仕合の種を蒔銭
- 江戸に隠れなき千枚分銅
- 備はりし人の身の程
- 茶の十徳も一度に皆
- 越前に隠れなき市立
- 身は燃え杭の小釜の下
- 伊勢海老の高買
- 堺に隠れなき樋の口過ぎ
- 能は桟敷から見てこそ
巻五
- 廻り遠きは時計細工
- 長崎に隠れなき思案者
- 火を喰ふ鳥も身を知りぬ
- 世渡りは淀鯉の働き
- 山崎に打出の小槌
- 水車は仕合せを待やら
- 大豆一粒の光り堂
- 大和に隠れなき木綿屋
- 借銭の書置き珍し
- 朝の塩籠夕べの油桶
- 常陸に隠れなき黄金分限
- 人はそれぞれの願ひに叶ふ
- 三匁五分曙のかね
- 作州に隠れなき悋気嫁
- 蔵合といふは九つの蔵持
巻六
- 銀のなる木は門口の柊
- 越前に隠れなき年越屋
- 見立てて養子か利発
- 武州に隠れなき一文よりの
- 銭屋
- 買置きは世の心やすい時
- 泉州に隠れなき小刀屋の
- 薬代
- 身代固まる淀河の漆
- 山城に隠れなき与三右が
- 水車
- 知恵を量る八十八の升掻
- 今の都に隠れなき
- 三夫婦を祝ふ
どうであろうか。これを読んだだけで大体の内容がわかるのは当時の町人、しかもかなり知識層の町人だと思える。従ってここで若干の注が必要だろう。
まずそのほとんどが「どこそこに隠れなき」とういう言葉を使っているのでいずれもそれぞれの土地で有名な人物または事物だということだ。そしてこの書が先にも指摘したように「大福新長者教」とあるように全国の有名な金持ちたちの話なのだ。その全国も北は越前、南は豊後と範囲は広い。ただ意外と言っていいかどうか、同一場所では「江戸」が5話で一番多い。「京」は3話、「大阪」は1話と意外に少ない。さて、西鶴は関西人である。大阪の町人の子として生まれ、育ったことは夙に有名である。だから意外と思えるのだが、実は西鶴は全国の話を書きたかった。そして当時新興地域だった「江戸」に最も関心があったと言える。大阪にはすでに語るまでもない大町人がいたに違いない。しかし、関心は今でいう「ベンチャー」?にあったのだと思える。さて、ここで疑問なのは西鶴がここで紹介しているエピソードや人物の話をどう取材したのかということだ。ここの6巻各5話計30話は作り物ではないはずだ。各地で有名な話だとすれば、その取材力にまず驚かされる。そして西鶴がどのようなスタンスでこうした話を紹介しているかだ。
西鶴のスタンス
さて、この30話は全て金持ちの話なのだが、いずれも最初から金持ちだった人はいないということだ。確かに親からの相続は大事である。これは西鶴も認めているし、はっきりそう書いている。しかし、その財産を作った親もやはり始めから金持ちだったわけではない。これはこの時代がいかに町人の勃興した時代であったかを窺わせる点だ。江戸時代というと身分制の強い時代というイメージだが、この書を読んでいると全くそんなイメージがない。むしろ下層にいた人物がその才覚・勤勉・幸運によって上昇していくさまが印象深い。米蔵に通って、こぼれ米を拾うことを皮切りに金持ちになった年老いた女性。江戸で大工の後をついて捨てられた木端を拾い集め、箸を作って財を成し、やがては材木屋にまでなった男。豆まきの大豆を拾い集め、それを蒔いて増やし、それをさらに田畑の溝に蒔いて大収穫し、やがて大百姓になった男。こうした話の人物はいずれも初めは下層にいた人物たちだ。この大豆の話の男は特に面白い。この男、大百姓になった後も実にいろんなことにチャレンジし、多くの農機具を発明開発したという。そして財産をなしたわけだが、それはその才覚ばかりではなく、その「始末」の良さによっていると西鶴は書いている。この「始末」という言葉はこの書にたびたび登場するが、これは倹約・質素を旨とする生活スタイルと言っていいものだ。この「始末」によって財を成した人の話は他にも登場するが、この男は徹底していて遺言でそれを子息にも強要した。しかし、子息はそれを守らなかった。遊びに手を出し、あっという間にその財を失ってしまう。こうした二代目が財を失う話は今でもよく聞くが、何も二代目だけでなく、財を成した本人も遊びであっという間に財を失う話もある。財を得るには多くの努力と才能とが必要だが、それを維持するにはこの始末が必要で、ちょっとした油断から財を失うこともあると西鶴は指摘する。
こうした金持ちに必要なものを整理して語っている話がある。これは貧乏を抜け出すための方法という形で語られている。貧病の妙薬「長者丸」の処方と禁忌という話だ。朝起五両、家職二十両、夜詰八両、始末十両、達者七両、これを調合して毎日飲めば必ず金持ちになるという。(ここでいう「両」は薬剤の場合は4匁をいうらしい)。ただし、「毒断」と言って薬の効用を阻害する食物として様々なことを挙げている。主に美食、女遊び、芸事、子供の贅沢などだ。「家職」は仕事そのものだから二十両と多いのは当たり前だが、ここでも次いで「始末」を十両としている点に注目したい。「毒断」も即ち「始末」の範疇だ。とすれば西鶴が一番強調したかった点は「始末」ということになろうかと思う。
しかし、この「長者丸」の処方には入っていなかったが、成功者の話の多くにはその「才覚」が関わっていることも注目していいと思う。先程の百姓の話もそうだが、この書に登場する成功者には他とは異なる「才覚」がある。他にはない「アイディア」が必ず成功のきっかけになっている。三井の商売の仕方はそれがはっきり表れているし、いわば逆転の発想の貧乏神を祀って成功した男にしても、誰もが考えないような発想で商売を成功させている。ただ「始末」だけでは成功はなかったはずである。いわば「始末」は成功後にこそ必要なものとしているのかもしれない。成功後、没落してしまった話もいくつかあるが、それはその「始末」に失敗した例ということになるのだろう。
ただ、西鶴は決してそうしたことを教訓じみた筆致で書いてはいないことも強調しておきたい。ただ、実際にあった話として書いている。しかも仏教的な教訓や儒教的な道徳を説くというスタンスがまるでないこともこの時代において特筆に値すると思う。これこそ町人的リアリズムと言えるのかもしれない。お金を全面的に取り上げたこと自体も新しかったし、まさに町人的スタンスだと言える。
おわりに
さて、西鶴はこの書の終わりに、次第に豊かになる庶民生活について語り、京・大阪・江戸の繁栄ぶりを語っている。まさに元禄期の江戸時代は繁栄の時代だったのかもしれない。そこを生きた西鶴が町人という視点でその繁栄を支えた町人を描いたのがこの『日本永代蔵』であった。
2024.05.01
この項、了