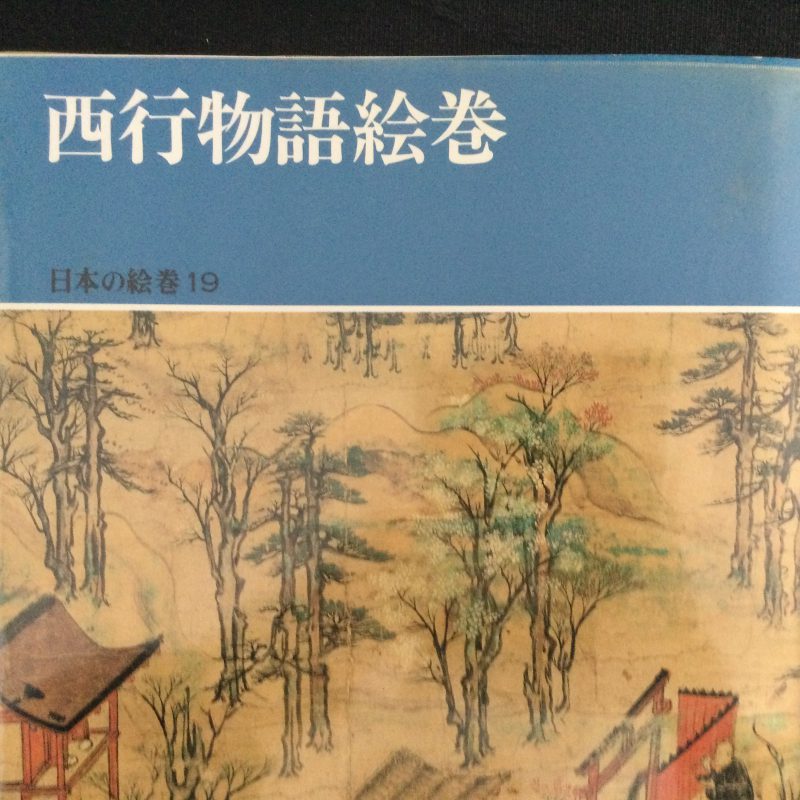久しぶりの古典文学総復習
今年も終わりになりそうなので、なんとかもう一冊ということで、今回は西行の『山家集』。
実はこれまでも西行についてはこの総復習で触れてきている。試みに検索すると6篇ほどで名前が挙がっている。
『千載和歌集』、『新古今和歌集』は当然のこと。『新古今和歌集』の項では「歌人別では一番多くの歌が取られているのがなんと西行である。94首ある。これは後鳥羽院の西行好きが影響しているのだろうか?」と書いている。『中世和歌集鎌倉編』には「西行晩年の最も小規模な自選詩華選」とした『山家心中集』がある。
また、『室町物語集上』には「歌人西行は多くの伝説があり、後の世にも多くを語られた人物だが、この物語は歌人としての西行よりも、恩愛の執着と葛藤する西行の発心・道心を印象深く簡潔に描いている」と書いた「西行」という物語がある。
さらには『とはずがたり』の項では「作者二条は幼いころ西行の旅の絵を見て旅に憧れたという記述が初めの方にある。」と書いている。
珍しいところでは江戸時代前期の狂歌集である『古今夷曲集』の中に西行を題材にした狂歌まである。
というようにいかに西行が日本の古典文学の中で大きな存在であるかがわかる。これは江戸時代の芭蕉や近代になってからの文学者たちからも敬愛され続けたことからも言える。いったいその理由は何なのだらろうか。単に、「優れた歌人で多くの名歌を残したから」、だけではないようだ。これは西行の人生にあるようだ。名門の武家であった(後の世に一世を風靡する平清盛といわば同僚であった)が、23歳の若さで突如出家し、その後は漂白に身をやつし、山に籠る生活を送ったとされるその人生選択が好まれるからのようだ。実際のところはどんな事情とどんな人生だったかはわからないが、この辺りは後の世に流布した「西行物語」や「西行物語絵巻」が果たした役割が大きいように思う。いわば伝説化した人物であったことには間違いはない。
さて、それはともかく、今回は西行の最大の個人歌集である『山家集』をしっかり読んでいくことにする。
『山家集』は個人歌集(私歌集)としては大部なものである。上中下三巻、1552首の歌を収める。
上巻は四季で、春173首、夏80首、秋237首、冬87首、計577首を収め、
中巻は恋と雑で、恋が134首、雑が330首、計464首
下巻は雑で511首(内恋100首)という構成になっている。
これらを全て詳細に読むことはできないので、3種の歌をとり挙げてみたいと思う。それは「花(さくら)」「月」、「恋」の歌である。実はこの3種のテーマの歌が極めて多いのだ。それに気づいた時、すぐに芭蕉のいわゆる歌仙式を思い出した。「なるほど」と一人で合点した。芭蕉は西行を敬愛していた。芭蕉たちによって完成した俳諧のいわゆる歌仙式は連歌の伝統から引き継いで三六句のうち必ず「ニ花三月」といって、「花」の句二句と「月」の句三句を詠むことになっている。(ちなみに「月」は定座といってきまったところで詠むことになっている)しかも「恋」の句も必ず含むように定められているのだ。しかしこれは余談。早速実際の歌を引いておく。(WEB上の優れた歌集「千人万首」に引かれた歌を中心に、ただし表記は「日本古典集成」の表記とする。)
先ずは「花」すなわち桜の歌から
64 おしなべて 花の盛りに なりにけり 山の端ごとに かかる白雲
66 吉野山 こずゑの花を 見し日より 心は身にも そはずなりにき
67 あくがるる 心はさても やまざくら 散りなむのちや 身にかへるべき
68 花見れば そのいはれとは なけれども 心のうちぞ 苦しかりける
76 花に染む 心のいかで 残りけん 捨て果ててきと 思ふわが身に
77 願はくは 花のしたにて 春死なん そのきさらぎの 望月の頃
78 仏には 桜の花を たてまつれ わが後の世を 人とぶらはば
108 いかでわれ この世のほかの 思ひ出でに 風をいとはで 花をながめん
118 もろともに われをも具して 散りね花 憂き世をいとふ 心ある身ぞ
119 思へただ 花のちりなん 木のもとに 何をかげにて わが身住みなん
120 ながむとて 花にもいたく 馴れぬれば 散る別れこそ 悲しかりけれ
134 風さそふ 花のゆくへは 知らねども 惜しむ心は 身にとまりけり
987 空わたる 雲なりけりな 吉野山 花もてわたる 風と見たれば
100首を超える「花」の歌から、筆者としてはいわば無作為に抽出したものだが、何か特徴がある気がする。それは「心」や「身」という言葉だ。桜の咲く、または散る情景を詠むというのではなしに、自分の「心」や「身」に、つまりは自分の「生」に関わるものとして花を詠んでいる気がする。有名な77番の歌は「その通りになった」と伝説に言われている歌だが、釈迦入滅の日(旧暦2月15日)に自分も死にたいという気持ちを歌ったというより、なにしろ満開の桜と自分が同化するようになりたいという願望のように思える。118番の歌などはその気持ちをズバリ歌っているように思えるのだが。
そして「月」の歌
311 播磨潟 灘の深沖に 漕ぎ出でて あたり思はぬ 月をながめん
333 うちつけに また来ん秋の 今宵まで 月ゆゑ惜しく なる命かな
349 月を見て 心うかれし いにしへの 秋にもさらに めぐりあひぬる
350 なにごとも 変はりのみゆく 世の中に 同じ影にて すめる月かな
351 夜もすがら 月こそ袖に 宿りけれ 昔の秋を 思ひ出づれば
353 ゆくへなく 月に心の すみすみて 果てはいかにか ならんとすらん
773 月を見て いづれの年の 秋までか この世にわれが 契りあるらん
774 いかでわれ 今宵の月を 身にそへて 死出の山路の 人を照らさん
1104 深き山に すみける月を 見ざりせば 思い出もなき わが身ならまし
1407 雲晴れて 身にうれへなき 人の身ぞ さやかに月の かげは見るべき
月については万葉の昔から多くの歌が作られてきたようだ。これは現代と違って、闇が深かった、昔の人々にとって、特別な感情を呼び起こす存在だったことによる。しかし「月並み」という言葉があるように歌や俳諧にとっての「月」は次第にありきたりな存在に成り果ててしまったようだ。西行にとってはどうだったか。ややその傾向が見え始めた時代だったかもしれない。しかし、もう一つ、仏教において「月」が特別な意味を持っていることに注目しなければならないといえる。「仏教では悟りの姿を月に見立てて、「真如の月」と言ったりもします。「真如」という言葉は、ありのままの姿、万物本体としての、永久不変の真理という意味があります。そして、「真如の月」と言った場合には、仏の教えの言葉となって、真如(永久不変の真理)によって煩悩の迷いが晴れるという意味になります。月の光は仏の慈悲の光と同じように考えられていたのかもしれませんね。」(京都芸術大学通信教育部ブログから)というように。西行の「月」はやはり月並みな情景としての「月」というより、仏教的な意味の「月」だった気がこれらの歌から読み取れるようだ。
最後に「恋」
617 知らざりき 雲居のよそに 見し月の かげを袂に やどすべしとは
618 あはれとも 見る人あらば 思はなん 月のおもてに やどす心は
620 弓張の 月に外れて 見し影の やさしかりしは いつか忘れん
621 おもかげの 忘らるまじき 別れかな 名残りを人の 月にとどめて
628 嘆けとて 月やはものを 思はする かこち顔なる 我が涙かな
644 くまもなき をりしも人を 思ひ出でて 心と月を やつしつるかな599 葉隠れに 散りとどまれる 花のみぞ 忍びし人に 逢ふ心地する
653 数ならぬ 心の咎に なし果てじ 知らせてこそは 身をも恨みめ
658 なにとなく さすがに惜しき 命かな あり経ば人や 思ひ知るとて
675 さまざまに 思ひ乱るる 心をば 君がもとにぞ 束ねあつむる
682 人は憂し 嘆きはつゆも 慰まず さはこはいかに すべき心ぞ
685 今ぞ知る 思ひ出でよと ちぎりしは 忘れむとての 情けなりけり
710 あはれあはれ この世はよしや さもあらばあれ 来ん世もかくや 苦しかるべき1269 逢ふまでの 命もがなと 思ひしに くやしかりける わが心かな
1320 いとほしや さらに心の をさなびて 魂切れらるる 恋もするかな
先に紹介したようにこの『山家集』には中巻と下巻に250首近くの「恋」の歌が収められている。僧侶であった西行にこれだけの「恋」の歌があるのは一見不思議である。しかし、「恋」は伝統的に歌のテーマであり、西行自身も出家以前には多分情熱的な「恋」を経験しているという。ここは前とのつながりからまず「月」と絡んだ「恋」の歌6首、「花」と絡んだ「恋」の歌1首、中巻の部立て「恋」から6首、下巻の「恋百首」から2首を引いておく。
さて西行は実際の「恋」を歌ったんだろうか。例えば621の歌、これなどは「後朝の別れ」が実体験的にあった上での歌のように思われる。また、自分より遠い存在の女性を思う気持ちが実際にあったようにも思われる。653の歌などはまさにそのことが率直に歌われている。また、710の歌などは西行にしか詠めない心の叫びと言っていい歌だ。
ここまで西行の歌を「花」「月」「恋」と絞ってみてきたが、他にも多くの優れた歌があるはずだ。しかし、今のところこれ以上は手に負えないので、今回はここまでにしておく。
2021.12.09
この項了