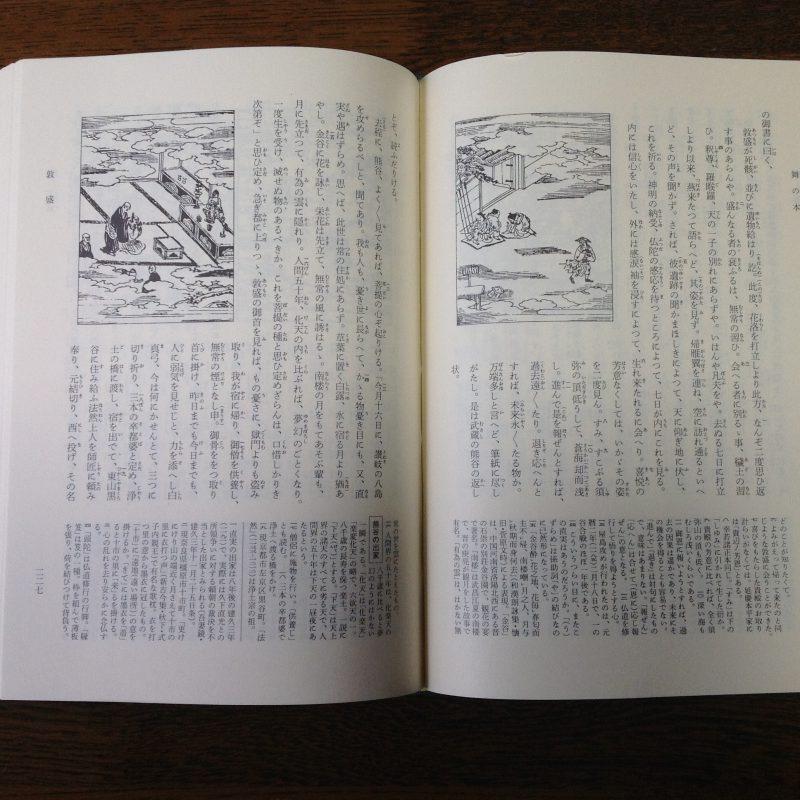前回「能・狂言」を取り上げたが、今回は幸若舞(こうわかまい)の本。幸若舞は「能・狂言」と違って、今やほとんど消滅してしまったものだが、当時は能よりも一般に支持されていたもので、むしろ能に先行する曲舞であったらしい。この『舞の本』はその幸若舞の台本となったものを読み物として絵入りで江戸期になって出版されたものだ。したがって、幸若舞がどうのような物であったかはこの本からはわからない。しかし、信長がこの舞を愛し、出陣の前に舞ったというセピソードは有名で多くの映画やテレビ番組で取り上げられているから想像はつく。ただ、映画やテレビはどうも「能」に近い物となっているようだ。また、「福岡県みやま市瀬高町大江に伝わる重要無形民俗文化財(1976年指定)の民俗芸能として現存している」ようだから見ることもできる。
ただここでは舞の様子ではなく、ここで取り上げられている「話」に注目したい。この『舞の本』は一つの読み物だからだ。
さて、この『舞の本』には36の話が収められているが、そのほとんどが軍記物語から取られているところに特徴がある。源平物が11編、義経物が11編、曽我物6編となっている。これはこの幸若舞が信長にみたように武士層に好まれた証拠である。軍記物語は読み物と言うより、語りや舞とともに普及していった。琵琶法師の語りがその代表だが、この幸若舞もその普及に寄与していたようだ。これは武士層が識字能力に劣っていたと言うこともあるかもしれない。また、実際の戦乱やそこでの人間模様を描くのに、語りや舞を伴ったほうが受け入れやすかったからかもしれない。そして、この『舞の本』はそれを絵入りで読み物化した。これも時代が江戸へ移り、識字能力の拡大と平和があったからこそかもしれない。またさらに、ここで語り継がれ、舞継がれて行った物語は様々に形を変えながらその後も生き延びて行く。江戸の浄瑠璃や歌舞伎の演目にもこの本にある物語から取られた物も多い。明治期に書かれた森鴎外の「山椒大夫」も出典がこの本にある「信田」にあるという。簡潔に言えば、この『舞の本』にある物語は日本人が「好き」な話なのだ。
その例を源平物の「敦盛」と説話系の「信田」に見てみたい。
「敦盛」はもちろん出典は『平家物語』である。『平家物語』の「敦盛最期」という章から大筋は捉えられている。話のポイントは平家の若き公達敦盛を打つ熊谷直実の心根にある。親として息子を持つ直実が同じような年頃の敵とはいえ少年の首をとることに逡巡し、(結局は首を取るが)武士として生まれたことを悔やむという話だ。
あはれ、弓矢取る身ほど口惜しかりけるものはなし。武芸の家に生まれずは、何とてかかる憂き目をば見るべき。情けなうも討ちたてまつるものかな」とかきくどき、袖(そで)を顔に押し当ててさめざめとぞ泣きゐたる。(『平家物語』から)
そして、この直実がその後、この件をきっかけに菩提心を起こし、法然の元で出家する。幸若舞の話はここが中心となる。つまりは熊谷直実が主人公となって、その勇猛果敢な武士の人間的面を強調する物語だ。以下は信長が好んだと言う直実発心の行。
去程に、熊谷、よくよく見てあれば、菩提の心ぞ起こりける。「今月十六日に、讃岐の八島を攻めらるべしと、聞いてあり。我も人も、憂き世にながらへて、かかる物憂き目にも、又、直実や遇はずらめ。思へば、此世は常の住処にあらず。草葉に置く白露、水に宿る月より猶あやし。金谷に花を詠し、栄花は先立て、無常の風に誘はるる。南楼の月をもてあそぶ輩も、月に先立て、有為の雲に隠れり。人間五十年、化天の内を比ぶれば、夢幻のごとくなり。一度生を受け、滅せぬ物のあるべきか。これを菩提の種と思ひ定めざらんは、口惜しかりき次第ぞ」と思い定め、
以下熊谷は都に上り敦盛の獄門首を盗み取って荼毘に付し、遺骨を奉じ、黒谷の法然上人の許に投じて出家するという展開となる。そしてこの行のうち
人間五十年、化天の内を比ぶれば、夢幻のごとくなり。一度生を受け、滅せぬ物のあるべきか。
の部分が信長の名とともに有名となる。信長が出陣の前にこの章句を語って舞ったという。この話は『信長公記』にあるというが、事実であるかはどうでもいい。あのかぶき者の信長らしからぬエピソードで、ここでも日本人の好みがわかる。
なお、この「敦盛」は能に歌舞伎に取り上げられることになる。
さて、もう一つ「信田」だが、これは軍記物とは様相が異なる。
いわば一種の貴種流離譚だ。もともと貴種であったものがある事情から騙され、人買いに売られ辛酸をなめることになる。しかし、あることをきっかけに復活し、復讐を遂げるという物語だ。出典は明らかでないが、先行する物語があった可能性がある。また、主人公が平将門の末裔という設定も東国の将門伝説を背景に持っていたとも思われる。後に説教浄瑠璃「しだの小太郎」として再生し、説経節の「山椒大夫」と共通性が強く、鴎外の「山椒大夫」へと受け継がれる。こうした話も伝統的に日本人が「好き」なのだ。
中世から近世に至る過程にあるこうした物語群は我々日本人の心根になっている気がする。
2017.09.12
この項了