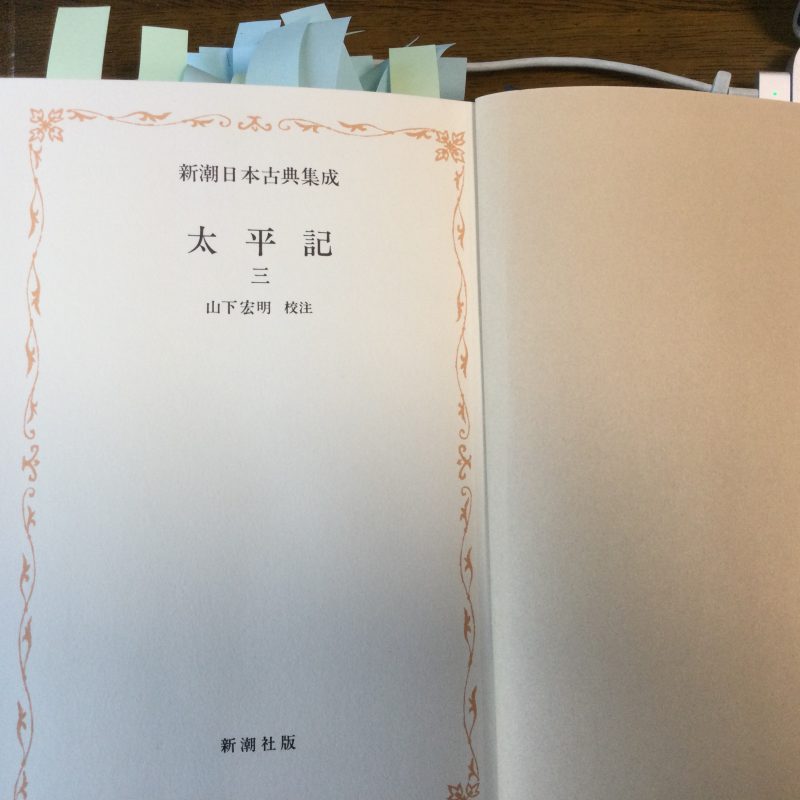『太平記』を読むその2
久しぶりに古典文学の記事、「太平記」の続編。
第二部、巻12から巻21までは、建武政権の乱脈を批判しつつ、諸国の武士の、新政に対する不満を背景に足利・新田の対立、足利の過去の善因による勝利、後醍醐天皇の吉野での崩御までを描く。
では各巻の概略を見ておこう。
巻12
新政権発足から、大塔宮護良親王が捕われ鎌倉へ護送・幽閉されるまでを描く。
王朝体制の回復が進むが、早くも大塔宮と足利高氏の対立が顕在化し、武士たちも論功行賞をめぐって不満を募らせ、社会は決して安定しない。また、大内裏造営の計画が進むが作者は北野天神縁起を長々と引いてこれが時代にそぐわないことを語る。
巻13
新政権内部の矛盾が引き続き現れ、北条残党の謀反も生じ、一時は北条残党が鎌倉を奪還するが、足利尊氏の活躍により平定され、足利尊氏の存在感が一躍脚光を浴びることを語る。
巻14
足利尊氏と新田義貞との対立抗争が中心的に語られる。足利尊氏と新田義貞はいわば論功行賞をめぐって対立し、戦うことになる。一時尊氏は恭順の意を示したりするが、結局は天皇をいただく新田義貞を京から天皇とともに追い出すことに一時的に成功する。ここにこの書の第二部の世界が展開し始める。
巻15
ここも尊氏と義貞の対立抗争が描かれる。この抗争がいわば全国展開を見せ、この巻では足利尊氏が九州に敗走するまでを描く。また、延暦寺と園城寺との対立がそれに絡んで語られ、俵藤太説話が語られたり、後醍醐天皇の失意の恋物語が語られたりする。
巻16
九州に到着した尊氏は九州を平定、その後再び京を目指し、新田軍・楠軍と湊川で戦い勝利する。ここで楠木正成は自害し、新田軍は京都へ退くことになる。後醍醐天皇は東坂本(比叡山)に難を避けるが、光厳院ら持明院統の人々は、尊氏の待機する東寺へ入る。
この巻ではなんといっても後々語られることとなる正成の自害とその子正行の話がクライマックスだろう。また、尊氏の正成に対する評価も見逃せない。
巻17
この巻は尊氏と新田義貞の一進一退の戦いの様を描く。
上洛を遂げた足利尊氏は、後醍醐天皇を匿い支援する山門(延暦寺)の攻略を図り、坂本で新田軍と戦うが、神仏に阻まれ敗退、これを新田軍が追って京を攻めるが、機を逸したため敗北、というように決着がつかない。
結局新田は東宮を擁して北国にのがれる。一方尊氏は天皇を幽閉して、新田のこもる金崎城攻略のため大群を差し向けるが、これも責め切れない。
巻18
最終的に尊氏の勝利を描く。
幽閉の身であった後醍醐天皇は花山院を脱出、吉野衆徒の協力を得て吉野へ臨幸、この知らせが新田軍の立てこもる金崎城へもたらされ城内の兵は活気ずくが、援軍のない金崎城は落城、新田義貞は脱出、しかし新田義詮は自害を遂げる。東宮も捕らえられ、尊氏の勝利は確実となる。
巻19
光厳天皇を重祚させた足利尊氏は将軍職につき、一門栄華を極める。
しかしながら、新田義貞ら南朝側の抵抗も各地で起きていることを描く。北条時行が先帝に拝謁、許されて尊氏討伐の勅許を得たり、奥州に下っていた北畠顕家が兵を挙げて、鎌倉に足利義光らを破って上洛の途についたり、といった具合だ。ただ、こうした動きに統一感はなく、結局は尊氏側の勝利となってしまう。
巻20
ここは新田義貞の最期を語る部分。
北陸にとどまっていた義貞は、大群を持っていながら、平泉寺の衆徒が味方する足利高経を攻めきれず、かえって藤島城に直接赴いて討ち死にしてしまう。やがて義貞の首が京の大路を引かれ獄門にかけられ、その北の方を始め京の人々の涙を誘う。
このことが南朝側の離散をうみ、諸国の趨勢は北朝側に有利に働き始める。かくて新田物語は幕を閉じる。
巻21
物語の展開が、編年の順序に従っていないのはいつものことで、史実に照らすと年次に混乱があるようだが、ここでも南朝側の抵抗と北朝側の結果的な勝利が描かれる。また、ついにここで後醍醐天皇の崩御が語られる。また、足利側の内部の不祥事が語られる。高師直と塩谷判官の話もここで語られる。いうまでもなく江戸時代の忠臣蔵が仮託した話だ。
以上が第二部。足利尊氏と新田義貞の戦いが中心となっている。そこに楠木正成の最後と後醍醐天皇の崩御が語られている。さて、この太平記の本文はどのようなものかも紹介しなければならない。楠木正成の自害の場面を引いておこう。
この勢いにても打ち破って落ちは落ちつべかりけるを、楠京を出しより、世の中の事今はこれまでと思ふ所存有ければ、一足も引かず戦ひて、機すでに疲れければ、湊川の北に当たつて在家の一村有ける中にへ走り入つて、腹を切らんために、鎧を脱いでわが身を見るに、斬り傷十一箇所までぞ負うたりける。(中略)正成座上に居つつ、舎弟の正季に向かつて、「そもそも最後の一念に依つて、善悪の生を引くといへり。九界の間に何か御辺の願ひなる」と問ひければ、正季からからとうち笑うて、「七生までただ同じ人間に生れて、朝敵を滅ぼさばやとこそ存じ候へ」と申しければ、正成よに嬉しげなる気色にて、「罪業深き悪念なれども、われもかやうに思ふなり。いざさらば同じく生を替へてこの本懐を達せん」と契つて、兄弟ともに差し違へて、同じ枕に臥にけり。
この「七生までただ同じ人間に生れて、朝敵を滅ぼさばやとこそ存じ候へ」という言葉が、後々尊氏が朝敵で正成が忠臣という図式を生むことになるが、実はこの「太平記」はどちらにも偏らない立場で書いているように思える。
今回はここまで。
2021.06.17