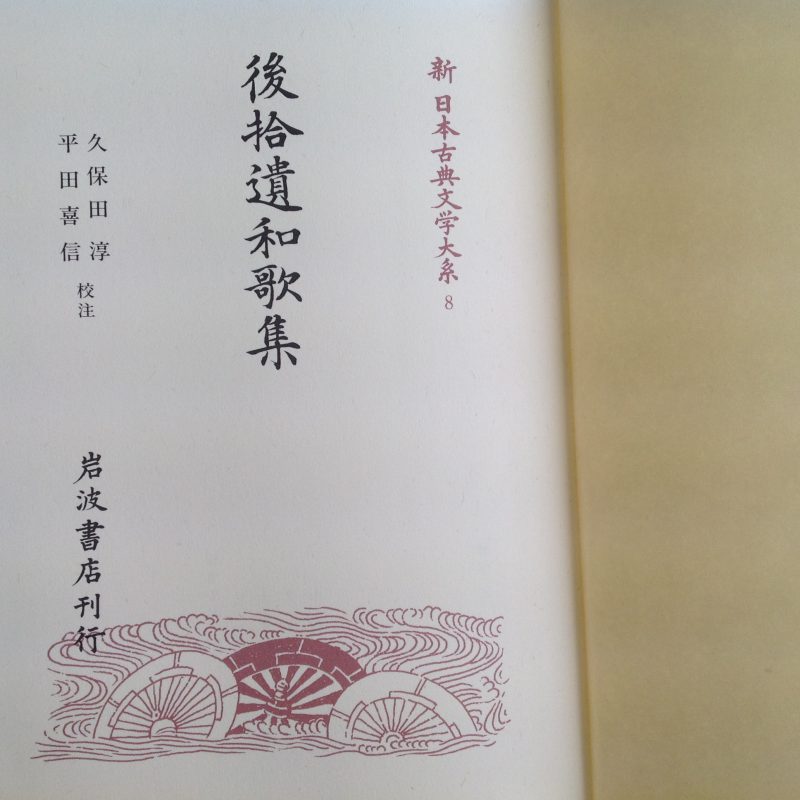Contents
『後拾遺和歌集』を読む
歌集について
『後拾遺和歌集』は名のとおり『拾遺集』の後に編まれた勅撰和歌集である。といっても80年以上経っていることは注目していい。
総歌数は1218首。構成はこれまでと同様20巻で春、夏、秋、冬、賀、別、羇旅、哀傷、恋、雑からなっている。特徴は巻二十(雑歌六)に「神祇」「釈教」の分類が初めてあらわれた点、『古今集』『後撰集』以後の歌が取られているが、紀貫之等のこの時代の代表的な歌人の歌がほとんどない点、主な歌人として、和泉式部(67首)・相模(39首)・赤染衛門(32首)といった女流歌人が多く取られている点などだ。
また、撰進当時から批判の声が高かったらしいが、これはこの集がこれまでの勅撰集のあり方から脱皮を目指したためだとも言える。
そこでここでは多く取られて女流歌人の歌を見ていくことにする。これは源氏物語を頂点とする世界に類を見ない女流文学の端緒とも言えるからだ。
歌人
小大君
いかに寝て起くる朝にいふことぞ昨日をこぞと今日をことしと
巻頭を飾る歌。作者の詳細は不明だが、古今集の巻頭の歌を念頭に置いた歌であることは疑いない。歌としては理屈が勝っていてどうかと思うが、巻頭に女性の古今集巻頭の歌のパロディ的な歌を置いた点にこの歌集の意気込みが感じられる。
古今集巻頭の歌は在原元方の以下の歌だ。
年の内に春は来にけりひととせを去年とやいはむ今年とやいはむ
紫式部
み吉野は春にけしきにかすめどもむすぼほれたる雪の下草
なかなか地上に現れない「雪の下草」は作者自身のことか。「むすぼほれたる」とは「根がもつれてほどけないでいる」意。心がふさいで晴れないと言っている。宮廷生活の一面か。
めづらしき光さしそふ月はもちながらこそ千代もめぐらめ
詞書きに「後一条院が生まれさせ給ひて、七夜に人々がまいりあひて、さかつきいだせと侍りければ」とあり、皇子誕生の祝いの歌。宮廷での華やかな面がうかがえる。
紫式部は言わずと知れた源氏物語の作者。もちろん多くの歌を残した。ただ、この女性、当代きっての批評家と言える。日記のなかで当代の女流をいろいろ批評している。後に引く清少納言はもっとも辛辣な批評を受けた人物。この集で多くの歌を取られている和泉式部についても歌や人物評をしている。これはこの女性たちがほとんど一条天皇の後宮に出仕していた女房仲間であったことも関係している。仲間という言葉を使ったが、「仲間」イコール「ライバル」という関係は今も昔も変わらない。
清少納言
夜こめて鳥のそらねにはかるともよに逢坂の関はゆるさじ
紫式部を出したら、この人を出さないと。言わずと知れた『枕草子』の作者の一首。百人一首にも取られた有名な歌。教養のひけらかしと紫式部に言われそうな歌。
この歌には「函谷関の故事」というのが背景にあって、中国の秦国に入って捕まった孟嘗君が逃げる時一番鶏が鳴くまで開かない函谷関の関所を部下に鶏の鳴き真似をさせて開けさせたというお話。長い詞書きがあって、宮中での出来事が語られている。
赤染衛門
帰る雁雲居はるかになりぬなりまた来ん秋も遠しと思ふに
やすらわで寝なましものをさ夜ふけてかたぶくまでの月を見しかな
さもあらばあれ山と心しかしこくはほそぢにつけてあらす許ぞ
赤染衛門も一条後宮の女房の一人。紫式部はこの人の歌を評価している。
最初の歌は清少納言と違って素直な歌ぶり。
引いた2番目の歌は百人一首に取られている。男をまって夜明かししてしまったことを言っているが、なんとも素直に恨みがましいところがない歌だ。ただ、これは詞書きによればある女のために詠んであげた歌ということになっている。和歌が貴族の日常生活で一般化するとこうした「代詠」はかなりあったと思われる。
3番目の歌は実はこの『後拾遺和歌集』の掉尾を飾る歌だ。この集は女流歌人に始まって女流歌人に終わっていることになる。この歌は大江匡衡の以下の歌の返歌。
はかなくも思ひけるかなちもなくて博士の家の乳母せんとは
これは乳の出が悪い乳母を置いたことを嘆く、父の歌。大江匡衡は文章博士。赤染衛門はその妻。従ってこの歌は妻の慰めの歌。「山と心」は「大和心」。後に「大和魂」と表記されてしまうが、元々は漢才すなわち知識とは違う日常の実際的な知恵や才覚をいう言葉だ。それがあれば、たとえ乳が細くても置いておきましょうと言っている。この歌は「雑六」の俳諧歌に分類されている。
相模
見わたせば波のしらがみかけてけり卯の花咲ける玉川の里
たのむるをたのむべきにはあらねども待つとはなくて待たれもやせん
最初の歌の詞書きに「絵合」をした時の冊子に書き付けたとある。「絵合」は平安時代の貴族の間で行われた遊び。左右2組に分れて小さな絵を出し合ってその優劣を競う。『源氏物語』の「絵合」の段にそのありさまがうかがわれる。
波が立っているところを柵に見立てた歌。
2番目の歌は和泉式部と並び称された相模ならではの歌。詞書きに男が待てと言ってきた返事の歌とある。「たのむ」と「待つ」という語を繰り返し上手く使う。「あなたの頼りない言葉を期待することはできない。でも、気がつくとあなたを待ってしまう。なんと頼りない私の心よ。」と言っている。恋二にある歌。
和泉式部
さびしさに煙をだにもたたじとて柴折しくぶる冬の山里
とどめおきて誰をあはれと思ふらん子はまさるらん子はまさりけり
黒髪のみだれも知らずうちふせばまづかきやりし人ぞこひしき
人の身も恋にはかへつ夏虫のあらはに燃ゆと見えぬ許ぞ
かるもかき臥す猪の床のいを安みさこそ寝ざらめかからずもがな
もの思へば沢のほたるもわが身よりあくがれ出づるたまかとぞ見る
こうなれば、和泉式部の登場だ。当時の最高貴族藤原道長に「浮かれ女」と言わしめた女性だ。後世にも様々な伝説に登場する。前に見た『拾遺和歌集』では1首しか取られてなかったが、この集では実に67首も取られている。選者の並々ならぬ傾倒ぶりが伺える。
1首目は冬に取られた歌。「たたじ」は「断つまい」ということ。単に寒さしのぎなのだろうが、そこに「さびしさ」に耐えようとする情景として詠む。こういう歌もある。
2首目は素直に子を思う気持ちを詠む。和泉式部には小式部内侍という歌人の娘があり、この娘との逸話は有名だが、この歌の子は別の子。和泉式部は多くの男と結婚しているが、この子は藤原範永との間にもうけた娘。この娘がが藤原公成の子を出産した際に20代で死去したらしい。この際母の和泉式部が詠んだ歌である。親の率直な心情が率直な言葉で歌われている。
3首目以降は何も言う必要はあるまい。じっくり鑑賞すれば足りる。
やはり和泉式部は当代きっての、いや今でも十分通づる「恋の歌人」である。
その他
津の国のなにはのことか法ならぬ遊び戯れまでとこそ聞け
雑六の「釈教」にある、遊女の歌。「遊女宮木」と作者名を記している。
これは性空上人という人が結縁の供養をした際、多くの人々が布施をしたが、遊女からの布施を受け取るのを躊躇したことに対する歌。
「仏法は遊女の身までを救ってくれるものと聞いていますが」と上人をやり込める。いいね。こういう歌を取っていることも注目してもいいと思われる。
女流歌人の歌ばかりを拾ってきたが、この『後拾遺和歌集』はその控えめな歌集名にもかかわらず、文学史上瞠目すべき歌集であることを知った。
歌の引用は適当な電子テキストがないため、『新日本古典文学大系』の表記を筆者が電子化したものである。
この項了