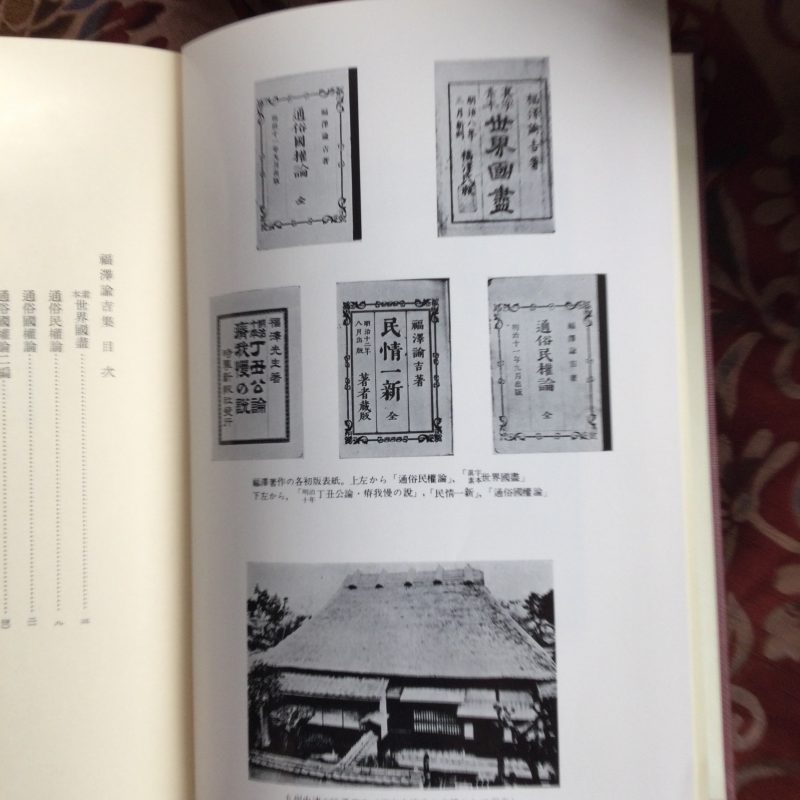Contents
はじめに
また少し間が空いてしまった。今回は半月で行けると思っていたが、途中にパソコンの改造の作業を入れてしまい、これが結構手こずってしまったので、やはり一月は要してしまいそうだ。
さて今回は個人集である。誰もが知っている福沢諭吉である。お札になったぐらいだから知らぬ人はほとんどいないと思うし、「学問のすすめ」の文言はどこかで必ず聞いたはずである。
ただ、福沢諭吉は文学者ではない。批評家というのともちょっと違う。しかし、日本近代を代表する「思想家」であることに間違いはない。これまでも文学者というより思想家をこの明治文学全集は取り上げてきているから不思議ではないが、その中でもこの人物は明治時代にあって外せない人物だから当然ということになろう。
ともかく改めてこの思想家の思想を読み解いていきたい。
福沢諭吉の思想
先ずは福沢諭吉の一般的な理解を紹介しておこう。ネットで検索すると以下のように書かれている。
AI による概要
福沢諭吉は、『慶應義塾の創設者』であり、明治時代の『啓蒙思想家』、**『教育家』**です。幕末に欧米の文化を『西洋事情』で紹介し、明治維新後は「学問のすすめ」などの著作を通じて、個人の自立と平等、そして学問の重要性を説きました。
慶應義塾の創設:1858年に蘭学塾を開き、これが現在の慶應義塾の源流となりました。
西洋文化の紹介:幕府の使節として欧米を訪れ、帰国後に『西洋事情』を著して、日本に西洋の知識を広く伝えました。
啓蒙思想の普及:「学問のすゝめ」を書き、人々に学問を勧めて個人の自立を促し、近代社会のあり方を示しました。
新しい言葉の創出:「自由」「演説」「社会」など、現代で当たり前に使われている多くの言葉を英語から訳して広めました。
明治政府に仕えず:明治維新後、政府からの要請を断り、教育活動と著作に専念しました。
間違いはありませんね。しかし、これだけでは福沢諭吉がいかに優れた思想家だったかは伝わりませんね。そこでこれからその著作を読んでいくことによってより深い理解をしていきます。そうするとこの福沢諭吉がいかに日本の近代において大きな人物だったかがわかるはずです。
収録作品の内容
「素本世界國盡」
冒頭で
「世界は廣し萬國は多しといへど大凡そ、五に分けし名目は亜細亜、阿弗利加、欧羅巴、北と南の亜米利加に、堺かぎりて五大洲、太洋洲は別に又、南の島の名稱なり。」
と述べて世界を州別に、そして各州では属する国々を挙げている。しかも七五調で分かりやすく覚えやすいように述べている。世界地理の教科書といったところ。
「通俗民權論」
緒言にある通り、これは上等社会の学者など知識人に対してではなく、俗世間の一般の人々に対して当時盛んに言われていた「民権」とは何かを福沢なりの考えで説いたものである。内容は八章にわたって述べられているが、基本は「一身独立」した「民」の力こそ重要であるという点に眼目があるとする。
「通俗國權論」「通俗國權論二編」
上記の通俗民權論脱稿後すぐに書かれたもの。ここでも基本は「一身独立」した「民」の力であり、それ無くして国の独立を維持・強化することはできないとするもの。一般的に「民権」と「国権」は対立し、相反する物のように考えられるが、福沢は「民権」あっての「国権」という考え方だ。その考えに基づいて自由民権運動、国会開設運動、条約改正問題等具体的政治課題を論じている。
「民情一新」
主に近代科学や産業革命によってもたらされた文明の力がその社会や人間を変えることを述べたもの。保守的な考え方ではなく、「進取の主義」によって国家のあり方や人間のあり方を変えていくことの重要性を説いたもので、それを理論的というより、具体的な制度や技術に沿って論じている。
「帝室論」
皇室は政治の枠外にあるべきことを説き。立場に関係なく全国民は同等に皇民であるとし、皇室は特定の政党に関与すべきではないことを主張したもの。現在の象徴天皇制に近い考え方が述べられている。「官権党」の結成を聞いた福澤が、その不適切なことを論じたもの。皇室の政治利用は危険であり、むしろ学問・芸術面での寄与こそ大事であるとする。
「尊王論」
基本的には前記の『帝室論』と変わらない趣旨。ただここで注意したいのは、同趣旨の論を改めて出版した経緯である。これは欽定憲法の起草、国会開設という点に絡んでいるようだ。福沢は繰り返し、帝室を政治外に置いておきたい考えが強くあったようだ。
「日本婦人論」
これは、女性の解放と自立を説いた先進的な論説。日本社会の長きに亘った男尊女卑の風習を打ち破るべく論じた婦人解放論と言える。その内容は、福沢が説く「一身独立」は女性にも応用されるべきものとし、女性に責任と財産を持たせること、そして封建的な男性の意識改革を促し、男女が独立した家族関係を築くべきであると主張している点が注目される。ここでも日本の民族が「人種改良」すべきことが述べられている。ここで面白いのは、結婚後に夫や妻の姓ではなく、新しい姓を創設すべきだと提言している点だ。これなどいわゆる「家制度」を根本から覆す論で、今話題の夫婦別姓どころではない気がする。
「實業論」
これは福沢諭吉の経済論集。ここでも国民の「一身独立」を説き、その経済活動こそ重要であること強調する。これは政府主導の経済からの脱皮を強調。背景には西南戦争後のインフレと松方デフレがあったと思われる。また、福沢は科学技術を背景にした「実業」の必要性を説く。これは実業界に未だ残っている封建的体質に対する批判である。しかもその批判は思想的な面からばかりでなく、変動するこの時代の経済状況を輸出入の数字や職工の賃金の世界比較をあげての分析からしている点も見逃せない。
ただ現実的には資本家が育っていないこの時代の日本の資本主義はどうしても国家主導にしかなり得ず福沢の理想は実現が難しかったのは歴史が示している。
「福翁百話」
これは、福沢諭吉が友人や来客との談話をまとめた100の随筆集。ここにはこれまで見てきた福沢の思想がさまざまな話題を通して述べられている。
注目すべき話題は「情欲は到底制止す可らず(四十五)」あたりだろうか。これは結局いい方策はないのだが、ここで福沢が人間の欲望を基本的に認めている点が重要だ。決して道徳的な方向に持っていこうとしていない点である。この考えは彼の「女性論」にも生きている。ぜひ読んで貰いたい一章である。以下の文言を引いておく。
「畢竟人生の情欲は制止す可きものにあらざれば、要は唯その方向を転じてこれを緩和するか、又は此れと彼れとを比較して害の少なき方に導くに在るのみ。(一部漢字変更)」
「福翁百餘話」
「福翁百話」と同じような趣旨で、随時に思いついた所感を書きとめたもので全十九編。
「明治十年丁丑公論」
これは、西南戦争の首魁である西郷隆盛を弁護し、明治新政府を批判した著書。著者は、西郷の行動を「横暴に対する抵抗」と捉え、明治新政府の統治に痛烈な批判を加えている。ここに福沢の明治新政府に対する根っからの抵抗感が窺える。ただ、この書は明治10年の西南戦争直後に執筆されというが、当時の取締法規に抵触する恐れがあったため、すぐには公刊されず福沢諭吉の死の直前である明治34年に『時事新報』紙上で発表されたという。
「瘠我慢の説」
この書は福沢の為人を知る上で重要であると思われる。また、これは明治維新に対する彼の立場を明確にする書でもあると言える。内容は明治維新前幕府側にあって重要な役割を示したが維新後明治政府に出仕した勝海舟と榎本武揚への批判で私信という形で書かれている。当初は発表の予定がなかったようだが、あるところから漏れてしまい地方の新聞に掲載されてしまったために前記の「明治十年丁丑公論」の一部として発表されものだ。
ここに福沢諭吉がやはり幕府側の人間であったこととそれ以上に明治新政府に対する反感が強かったことを示している。実は明治政府は政権を取ったものの全く人材不足であった。それまで官僚機構を高度に築きあげていた幕府には有用な人物が多数いた。これは「啓蒙思想集」でも見たように近代化にいち早く取り組んでいたのは実に幕府側の有意な若者たちだった、ということもあった。つまり明治政府にとって幕府側の人間は必要だったわけだ。「啓蒙思想集」に登場した多くの幕府側の若者たちも明治政府に何らの形で参加しているし、勝海舟はともかく、最後まで抵抗した榎本武揚までも受け入れたのだ。したがって福沢も政府への出仕を誘われている。前に取り上げた栗本鋤雲も然りである。しかし、福沢や栗本はそれを断っている。それを「瘠我慢」だとしている。そして彼らにはそれが足りないとしているのだ。ここにむしろ福沢の旧武士的な気概を見るのは私だけだろうか。好きだなこういう人物。ここに小栗上野介の無念や成島柳北の反社会的な姿勢を思わないいわけにはいかない。
「舊藩情」
これは、福沢諭吉が江戸時代における武士の厳格な身分制度と、家柄や血筋に縛られた「格差社会」の問題点を鋭く批判した著作だ。こうした論は自身がいわば下級の身分のしかも末っ子であった経験から論じられている。具体的に福沢が属した九州の小藩である中津藩の幕末から維新期にかけての実情を紹介している。そんな中、福沢は混乱期に自らの才能と努力によって確固とした地位を築いた(もちろんそれは政府の中ではないが)。そしてそれは何よりも「学ぶ」ことの重要性、その場である平等な学校の必要性を説いている。
「書翰集」
実に様々な人物に当てた書簡が収められている。書簡といっても一種論文のようなものもある。それぞれの内容についてはここで紹介はできない。
「諸文集」
福沢は本当に多くの文章を書いたものだ。ここには未発表のものや完本にならなかった短文が集められている。その中で小生が注目したのが「農に告るの文」という短いエッセイだ。これまで福沢の文章を色々読んできて感じたことの一つは農業や農民についてあまり語っていない点だ。福沢は近代主義者で殖産興業論者だから当然と言えば当然だが、実は日本の近代史において農業の問題は極めて大きいのだが、そこを福沢がどう見ていたかというのが興味深かった。さてこの短文でまず小作人の江戸時代から変わらぬ貧しい現実を描いて同情を寄せている。しかし結語では貧しさから抜け出すには「一日も早く無学文盲の閂を破る可き」だとして、全くどうして構造的に農民が貧しいかなど疑問すら提示していない。ここに福沢の考え方の特徴が見えている。今でも見え隠れするが、貧しさは「自己責任」だという自己責任論みたいである。ここは今後福沢の思想を考える上での一つの問題である。ここではこれ以上触れることはできない。
おわりに
ここまで福沢諭吉の文章を読んできたが、ここには代表作の『学問のすゝめ』と『文明論之概略』が掲載されていない。それは他でも読めるし、有名だからということらしい。実際小生も別の全集(中央公論社「日本の名著」33)で読んでいる。また青空文庫でも多くの著作が電子化され、また作業中ということだ。福沢諭吉は日本の近代が生んだ大きな思想家であることに疑いはない。今後も多くの人に読んで貰いたい。この小生の拙い文章がそのきっかけになってくれればいいと思っている。
2025.11.20
この項 了