『源氏物語』を読む2
今回は原文と与謝野晶子氏の訳文を引いて『源氏物語』で重要な部分を見てみる。
まず、源氏が義母である藤壺の宮と密会する場面である。
本文「若紫」から(本文は大系の本文を筆者が電子化したもの。以下同)
藤壺の宮、なやみ給ふことありて、まかで給へり。上の、おぼつかながり嘆ききこえたまふ御けしきも、いといとおしう見たてまつりながら、かかるおりだにと、心もあくがれまどひて、いづくにもいづくにも、参うで給はず、内にても里にても、昼はつれづれとながめくらして、暮るれば、王命婦を責め歩き給。
いかがたばかりけむ、いとわりなくて見たてまつるほどさへうつつとはおぼえぬぞ、わびしきや。
宮も、あさましかりしをおぼし出づるだに世とともの御もの思ひなるを、さてだにやみなむ、と深うおぼしたるに、いとうくて、いみじき御けしきなるものから、なつかしうらうたげに、さりとてうちとけず心ふかうはづかしげなる御もてなしなどのなほ人に似させ給はぬを、などかなのめなることだにうちまじり給はざりけむ、とつらうさへぞおぼさるる。
何事をかは聞こえつくし給はむ、くらぶの山に宿りも取らまほしげなれど、あやにくなる短夜にて、あさましう中々なり。
見ても又逢ふ夜まれなる夢のうちにやがてまぎるるわが身ともがな
とむせかへり給ふさまもさすがにいみじければ、
世語りに人や伝へむたぐひなくうき身を覚めぬ夢になしても
おぼし乱れたるさまも、いとことわりにかたじけなし。命婦の君ぞ御なをしなどはかき集め持て来たる。
殿におはして、泣き寝に臥し暮らし給ひつ。御文なども例の御覧じ入れぬよしのみあれば、常のことながらも、つらういみじうおぼしほれて、
内へもまひらで二三日籠もりおはすれば、又いかなるにかと御心動かせ給ふべかめるも、おそろしうのみおぼえ給ふ。
例によって難渋な文。主語が明記されていないから誰の行為かがわかりにくい。これは当時の敬語の使用法に我々が習熟していないためと言えるが、
もともとこの物語が極めて狭い世界で流通していた事も関係すると言える。主語をいちいち示さなくても読者にはわかるからだ。
与謝野晶子氏の訳文(「青空文庫」から。以下同)
藤壺の宮が少しお病気におなりになって宮中から自邸へ退出して来ておいでになった。帝が日々恋しく思召す御様子に源氏は同情しながらも、
稀にしかないお実家住まいの機会をとらえないではまたいつ恋しいお顔が見られるかと夢中になって、それ以来どの恋人の所へも行かず宮中の宿直所ででも、二条の院ででも、昼間は終日物思いに暮らして、王命婦に手引きを迫ることのほかは何もしなかった。王命婦がどんな方法をとったのか与えられた無理なわずかな逢瀬の中にいる時も、幸福が現実の幸福とは思えないで夢としか思われないのが、源氏はみずから残念であった。
宮も過去のある夜の思いがけぬ過失の罪悪感が一生忘れられないもののように思っておいでになって、せめてこの上の罪は重ねまいと深く思召したのであるのに、またもこうしたことを他動的に繰り返すことになったのを悲しくお思いになって、恨めしいふうでおありになりながら、柔らかな魅力があって、しかも打ち解けておいでにならない最高の貴女の態度が美しく思われる源氏は、やはりだれよりもすぐれた女性である、なぜ一所でも欠点を持っておいでにならないのであろう、それであれば自分の心はこうして死ぬほどにまで惹ひかれないで楽であろうと思うと源氏はこの人の存在を自分に知らせた運命さえも恨めしく思われるのである。源氏の恋の万分の一も告げる時間のあるわけはない。永久の夜が欲ほしいほどであるのに、逢わない時よりも恨めしい別れの時が至った。
見てもまた逢夜稀なる夢の中うちにやがてまぎるるわが身ともがな
涙にむせ返って言う源氏の様子を見ると、さすがに宮も悲しくて、
世語りに人やつたへん類なく憂き身をさめぬ夢になしても
とお言いになった。
宮が煩悶しておいでになるのも道理なことで、恋にくらんだ源氏の目にももったいなく思われた。源氏の上着などは王命婦がかき集めて寝室の外へ持ってきた。
源氏は二条の院へ帰って泣き寝に一日を暮らした。手紙を出しても、例のとおり御覧にならぬという王命婦の返事以外には得られないのが非常に恨めしくて、源氏は御所へも出ず二、三日引きこもっていた。これをまた病気のように解釈あそばして帝がお案じになるに違いないと思うともったいなく空恐ろしい気ばかりがされるのであった。
さて、これは前半の山場。若い源氏が父の後添えである藤壺の宮が里下がりをしていた時に侍女を手引きに逢う場面だ。源氏は幼い時からこの藤壺の宮に親しんできた。それはこの藤壺の宮が亡き母に生き写しだったからだ。この亡き源氏の母は帝が寵愛の限りを尽くした女性だ。身分が低く、帝の寵愛を受ければ受けるほど周りの他の妻たちからからいじめにあった。そのせいか若くしてこの世を去ってしまう。したがって息子の源氏にはこの母の記憶がない。だからこそ余計に母に似た年齢のあまり違わない義母への思慕が募っていった。それがやがて恋情となり、ついに禁を犯してしまう。この場面以前にもすでに二人は逢瀬をしていた事が「宮も、あさましかりしを」という表現でわかる。与謝野晶子はこれを正確に「宮も過去のある夜の思いがけぬ過失の罪悪感」と翻訳しているように暗に過去の間違いをここで示している。
さて、今度は後半の主要な場面。源氏が新たに迎えた妻、女三宮が柏木に強引に襲われる場面だ。
本文「若菜下」から
宮は、何心もなく大殿籠もりにけるを、近くおとこのけはひのすれば、院のおはする、とおぼしたるに、うちかしこまりたるけしき見せて、床の下に抱きおろしたてまつるに、ものにをそはるるかと、せめて見上げ給へれば、あらぬ人なりけり。あやしく聞きも知らぬことどもをぞ聞こゆるや。あさましくむくつけくなりて、人召せど、近くもさぶらはねば、聞きつけてまいるもなし。わななき給ふさま、水のやうに汗も流れて、ものもおぼえ給はぬけしき、いとあはれにらうたげ也。
「数ならねど、いとかうしもおぼしめさるべき身とは思給へられずなむ。むかしよりおほけなき心の侍しを、ひたぶるに籠めてやみ侍なましかば、心のうちに朽たして過ぎぬべかりけるを、中々漏らしきこえさせて、院にも聞こしめされにしを、こよなくもて離れてものたまはせざりけるに、頼みをかけそめ侍て、身の数ならぬ一際に、人より深き心ざしをむなしくなし侍ぬることと、動かし侍にし心なむ、よろづいまはかひなきこと、と思給へ返せど、いかばかりしみ侍にけるにか、年月に添へて、くちおしくも、つらくも、むくつけくも、あはれにも、色々に深く思給へまさるにせきかねて、かくおほけなきさまを御覧ぜられぬるも、かつは、いと思ひやりなくはづかしければ、罪をもき心もさらに侍るまじ」
と言ひもてゆくに、この人なりけり、とおぼすに、いとめざましくおそろしくて、つゆいらへもし給はず。
「いとことわりなれど、世にためしなきことにも侍らぬを、めづらかになさけなき御心ばへならば、いと心うくて、中々ひたふるなる心もこそつき侍れ、あはれとだにのたまはせば、それをうけたまはりてまかでなむ」とよろづに聞こえ給。
与謝野晶子氏の訳文
宮は何心もなく寝ておいでになったのであるが、男が近づいて来た気配をお感じになって、院がおいでになったのかとお思いになると、その男はかしこまった様子を見せて、帳台の床の上から宮を下へ抱きおろそうとしたから、夢の中でものに襲われているのかとお思いになって、しいてその者を見ようとあそばすと、それは男であるが院とは違った男であった。これまで聞いたこともおありにならぬような話を、その男はくどくどと語った。宮は気味悪くお思いになって、女房をお呼びになったが、
お居間にはだれもいなかったからお声を聞きつけて寄って来る者もない。宮はお慄い出しになって、水のような冷たい汗もお身体からだに流しておいでになる。失心したようなこの姿が非常に御可憐かれんであった。
「私はつまらぬ者ですが、それほどお憎まれするのが至当だとは思われません。昔からもったいない恋を私はいだいておりましたが、結局そのままにしておけば闇やみの中で始末もできたのですが、あなた様をお望み申すことを発言いたしましたために、院のお耳にはいり、その際はもってのほかのこととも院は仰せられませんでした。それも私の地位の低さにあなた様を他へお渡しする結果になりました時、私の心に受けました打撃はどんなに大きかったでしょう。もうただ今になってはかいのないことを知っておりまして、こうした行動に出ますことは慎んでいたのですが、どれほどこの失恋の悲しみは私の心に深く食い入っていたのか、年月がたてばたつほど口惜くちおしく恨めしい思いがつのっていくばかりで、恐ろしいことも考えるようになりました。またあなた様を思う心もそれとともに深くなるばかりでございました。私はもう感情を抑制することができなくなりまして、こんな恥ずかしい姿であるまじい所へもまいりましたが、一方では非常に思いやりのないことを自責しているのですから、これ以上の無礼はいたしません」
こんな言葉をお聞きになることによって、宮は衛門督であることをお悟りになった。非常に不愉快にお感じにもなったし、怖しくもまた思召されもして少しのお返辞もあそばさない。
「あなた様がこうした冷ややかなお扱いをなさいますのはごもっともですが、しかしこんなことは世間に例のないことではないのでございますよ。あまりに御同情の欠けたふうをお見せになれば、私は情けなさに取り乱してどんなことをするかもしれません。かわいそうだとだけ言ってください。そのお言葉を聞いて私は立ち去ります」とも、手を変え品を変え宮のお心を動かそうとして説く衛門督であった。
これは源氏が栄華を極め、六条院という広大な邸宅で豪華な生活をしていた時の話。
その六条院に迎えた新しい若い妻、女三宮という女性にかつての友人の息子である柏木という若い男が、謂わば押し入って想いを遂げようとする場面だ。実は夫である源氏はこの柏木が自分の若い妻に懸想している事を知っている。それは柏木の「院にも聞こしめされにしを、こよなくもて離れてものたまはせざりける」という言に伺える。訳では「院のお耳にはいり、その際はもってのほかのこととも院は仰せられませんでした。」とある部分だ。「院」とは源氏のこと。源氏は女三宮にそれほどの愛情を持っていないようにみえる。しかし、この柏木の行為が後に思わぬ運命のあやとなってしまう。すなわち女三宮はこの柏木の子を身ごもり、その子がこの物語の第二部の主人公薫大将となるからだ。やがて二人は罪の恐ろしさにおののき、出家を遂げることになる。この事件は源氏にとってかつて自分が若い時に犯した罪の復讐のように感じられたのかもしれない。
さて、ここで重要なのは、源氏と藤壺の密会と女三宮と柏木の密会の大きな違いである。両者とも夫ある身の女性と若い男性との密会だし、女の側に両者とも男を受け入れる意思はない。これは当時の婚姻形態が成せる技かもしれない。しかし、柏木の行為はほとんど強姦とも思えるが、源氏の行為は多少なりとも藤壺にも受け入れる余地があるように描かれているように思える。これは身分的な違いということもあろうし、物語的にも主人公と脇役といった違いもあろう。ただ、源氏の行為は亡き母の面影を持つ義母と関係を持ってしまうと言うところに重要性がある。これは源氏が後に多くの女性たちと関係を持つことと全く趣を異にしている。ましてや柏木と女三宮との関係とも次元が違うように思う。ここにはこの物語の肝が隠されている。帝の妻を犯すこと、自分の義母とはいえ実母の面影を持つ女性と関係を持つこと、これは当時にあっても重大な禁忌であるはずだ。作者紫式部はどんな思惑からこんな話にしたのか、解かねばならない課題である。
今回はここまでとする。次は重要な他の女性たちとの話を見て行きたい。
この項了
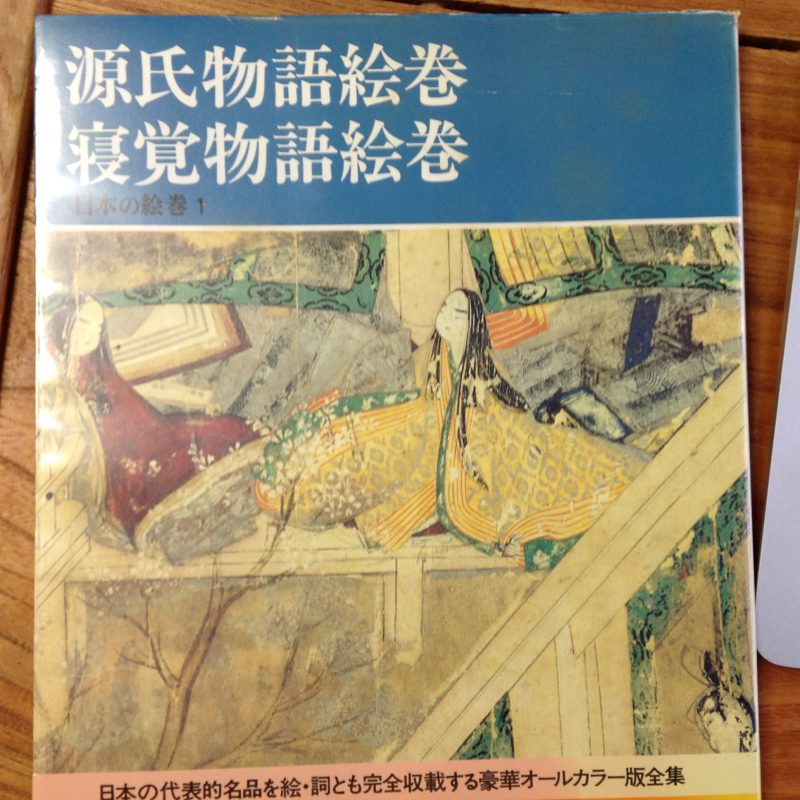
大学の時、数学ではなく源氏を専攻すればよかったと、本気で思ったことがあるのを思い出しました。でも、大人になっても勉強すればよいのですね。
どうもありがとう。老後の道楽には学問が一番ですね。これは江戸時代からの伝統です。ナンテネ。学問とは言えないけどね。