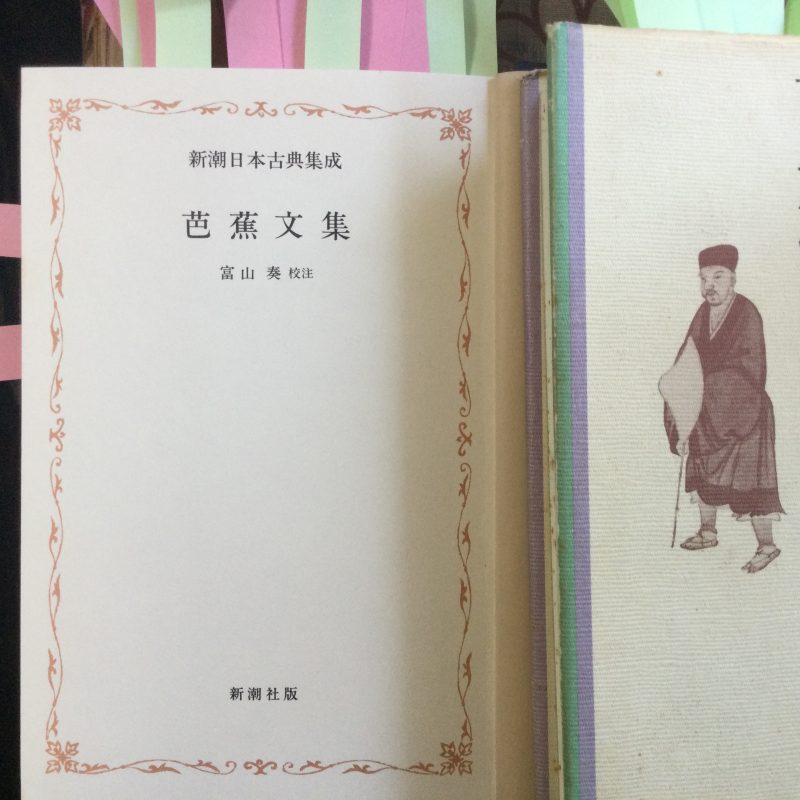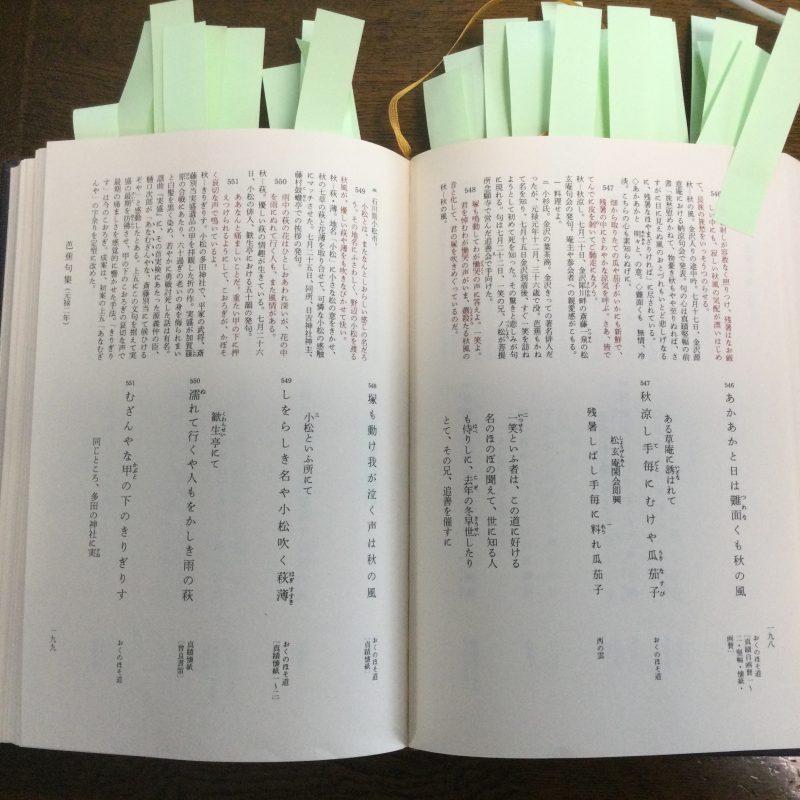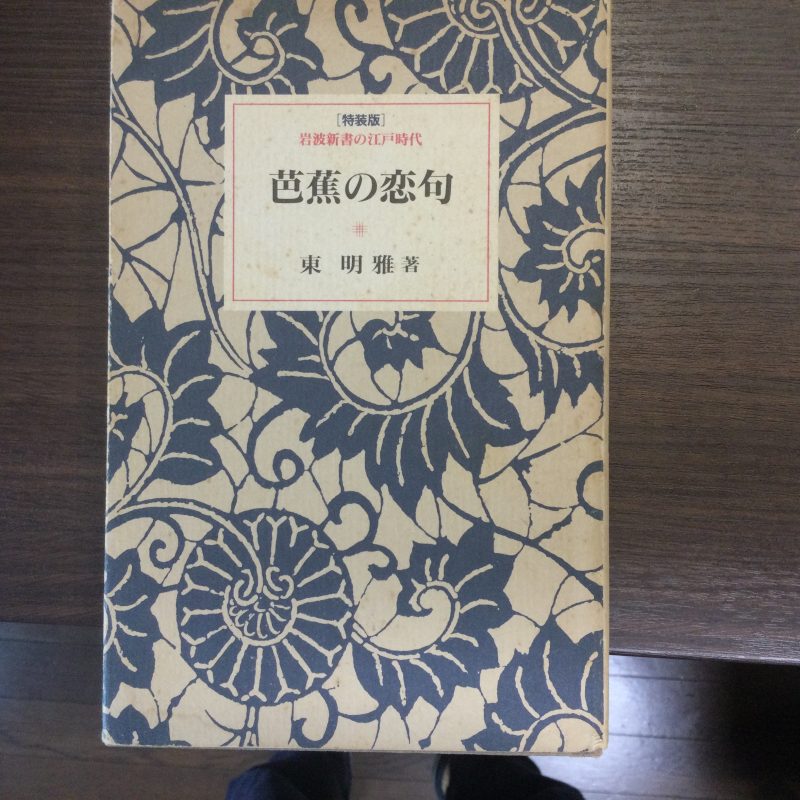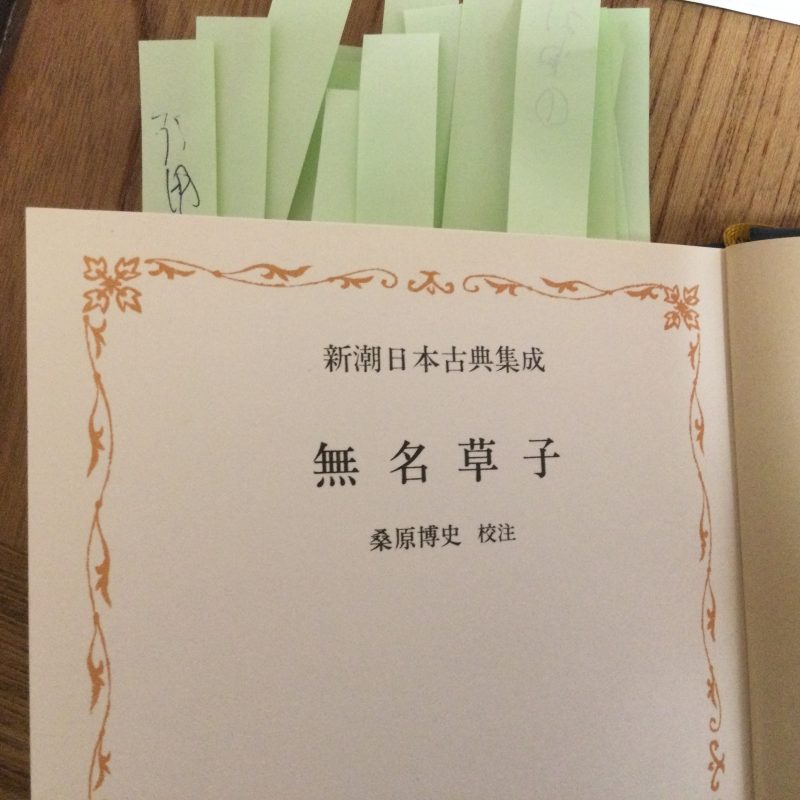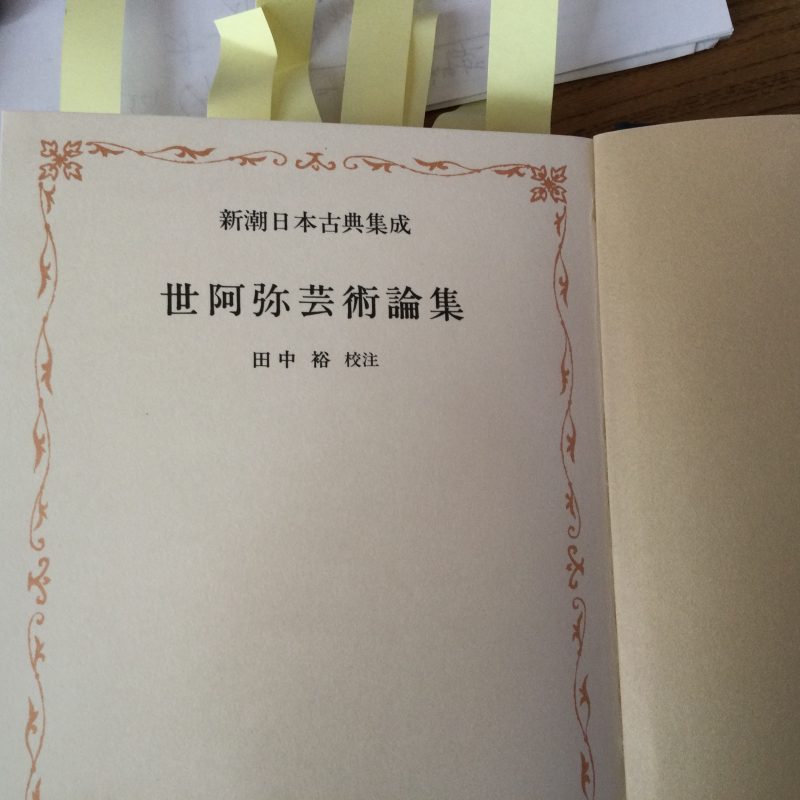はじめに
今回は『芭蕉文集』である。
この書には芭蕉37歳から逝去直前までの文章69篇が年代順に並べられて収められている。中身は数行の短い文書や書簡、「おくのほそ道」を代表する紀行文など、さまざまである。
それをここでは便宜上4種に区分けして読んで行きたいと思う。以下である。
- その一 断簡・短文 30篇
- その二 紀行文等 7篇 (厳密には紀行文ではないが「幻住庵の記」などを含む)
- その三 書簡 28篇
- その四 遺書 4篇
そしてそれぞれについて小生なりの読みを語りたいと思うのだが、その全てを紹介するわけにもいかないのでこの分類から幾つかを選んで語りたいと思う。
その一 断簡・短文
この類は素晴らしいものが多いのだが、ここでは以下の2篇を取り上げてみたい。参考に本文も示しておく。(番号は本書の番号)
「雪丸げ」と題された 四十三歳の作
曾良何某は、このあたりに近く、仮に居をしめて、朝な夕なに訪ひつ訪はる。我くひ物いとなむ時は、柴折りくぶる助けとなり、茶を煮る夜は、来たりて軒をたたく。性隠閑を好む人にて、交り金を断つ。ある夜、雪を訪はれて、
ばせを
きみ火をたけよき物見せん雪丸げ
ここでいう曾良何某は「奥の細道」の旅に同行した河合曽良のことである。芭蕉に入門まもない頃の俳文。この頃芭蕉は深川の芭蕉庵に暮らしていた。いわばわび住まいだが、その生活ぶりが窺われる。曽良はよっぽど芭蕉に心酔していたのだろう、なにくれと芭蕉の面倒をみていたようだ。芭蕉もすっかり信頼し、共にいることに喜びを感じていたようだ。それが句によく表れている。「雪まるげ」とは今で言う「雪だるま」だろうか。子供のような気分が窺えて、楽しい句だ。
「秋の朝寝」と題された 五十一歳の作
あるじは、夜あそぶことを好みて、朝寝せらるる人なり。宵寝はいやしく、朝起きはせはし。
おもしろき秋の朝寝や亭主ぶり 翁
これは芭蕉最晩年の俳文。大阪での半歌仙興行の翌朝の吟。その半歌仙の発句と脇は以下。
秋の夜を打ち崩したる咄かな 翁
月待つほどは蒲団身に巻く 車庸
その脇(俳諧の二句目。亭主が詠むことになっている。ちなみに発句は客が詠む、ここは芭蕉)を詠んだ車庸が「朝寝」をしている亭主だ。その朝寝坊している亭主ぶりに客芭蕉はなんとも心楽しいと言っている。晩年も変わらず心優しい芭蕉である。
その二 紀行文等
その梗概
紀行文としてはいわば滞在記も含めると以下の文がある。(番号は本書の番号)まずはその梗概を示しておく。
- 七 野ざらし紀行 四十一歳〜四十二歳・四十四歳完成
- 一五 鹿島詣 四十四歳
- 一六 笈の小文 四十四歳〜四十五歳・没後門人編成
- 二三 おくのほそ道 四十六歳・五十一歳完成
- 一九 更科紀行 四十五歳
- 二八 幻住庵の記 四十七歳
- 三五 嵯峨日記 四十八歳
「野ざらし紀行」は貞享元年8月、門人苗村千里を伴って深川の芭蕉庵を出立、東海道を上って伊勢・伊賀・大和を経て、以後は単独で吉野、9月下旬に美濃大垣、桑名・熱田・名古屋から伊賀上野に帰郷して越年、春の大和路をたどって京都へ出て、近江路から江戸への帰路のおよそ8ヶ月の紀行を題材とする作品。
「鹿島詣」は貞享4年8月、鹿島神宮に参詣し、芭蕉参禅の師といわれる仏頂和尚を訪ねて1泊し、雨間の月見をした短い旅の記録。
「笈の小文」は貞享4年10月に江戸を出発し、尾張、伊賀、伊勢、吉野、奈良、大坂、須磨、明石などを巡った7か月の旅の間に記録した断簡を弟子の乙訓が死後まとめたもの。
「おくのほそ道」は最もまとまった紀行文。後述。
「更科紀行」は貞享5年8月に門人越人を伴い岐阜を出発し、木曾街道を経て夜に更科に到着し、姨捨山の名月を見て、善光寺より碓氷峠を経て8月下旬、江戸へ帰るまでの紀行文。
「幻住庵の記」は、紀行文とはいえないが、一種の滞在記。「おくのほそ道」の旅を終えた翌年の4月~7月(陽暦の5月~9月)までの4か月を滋賀県大津にある国分山の幻住庵に暮らした。その時の記録。
「嵯峨日記」は、これも紀行文とは言えないが、元禄4年4月18日から5月4日まで、京都嵯峨の落柿舎に滞在した時の日記。芭蕉の滞在生活や、門下生との交流が記されいる。
「おくのほそ道」について
さて、これらの紀行文のうち最もまとまったものであり、古来人口に膾炙した作品はなんと言っても「おくのほそ道」である。ここで私なりの読みを語りたいと思う。
どうもこの作品が芭蕉を漂白の俳人というイメージを作り上げたように思う。確かに芭蕉は漂白の孤独な詩人を気取ってみたかったに違いない。しかし実態は必ずしもそうではないと思うのだ。また、この作品は現代的な意味でいう紀行文的なものでは決してないように思える。例えば有名な以下の句。
荒海や佐渡によこたふ天の川
この句を単独で読むと、いかにも男性的な日本海の風景が思い浮かぶし、それを眼前にしている孤独な芭蕉の姿が思い浮かぶ。しかし、この句の前に以下の叙述がある。
(前略)この間九日、暑湿の労に神を悩まし、病おこりて事をしるさず。
文月や六日も常の夜には似ず
この「荒海や」の句の前にある「文月や」の句は七夕のことを言っている。一日前だけれどもすでになんとなく「常の夜」とは違うと。織姫と牽牛を隔てた「天の川」、それが荒海の向こうにある佐渡との間に横たわっていると。つまり「佐渡」は実景として見えているのではなく、悲痛な島流しの歴史を持つ島として見えている。この句は頭注で編者の言う
実景の忠実な描写ではなく、旅懐と史的懐古とによる心象風景として構成した吟
なのだろう。この部分の地の文にはこの地の情景描写はひとつもない。
このことはある意味この作品の特徴とも言えそうだ。つまり紀行文というと実景の描写を期待するが、実景の描写が意外に少ないように思われる。あったとしてもそこに芭蕉ならではの特徴がある。以下は少ない実景描写の代表的な部分である。古来芭蕉の名文の誉が高い部分だ。
そもそも、ことふりにたれど、松島は扶桑第一の好風にして、およそ洞庭・西湖を恥ず。東南より海を入て、江の中三里、 浙江の潮をたたふ。島々の数を尽して、欹ものは天をゆびさし、伏すものは波にはらばふ。或は二重にかさなり三重にたたみて、左にわかれ右につらなる。負へるあり抱けるあり、児孫愛すがごとし。松の緑こまやかに、枝葉潮風に吹きたわめて、屈曲おのづから矯たるがごとし。そのけしき窅然として、美人の顔を粧ふ。ちはやぶる神の昔、大山祗のなせるわざにや。造化の天工、いづれの人か筆をふるひ、ことばを尽さむ。
雄島が磯は地つヾきて海に出たる島なり。雲居禅師の別室の跡、坐禅石などあり。はた、松の木かげに世をいとふ人もまれまれ見えはべりて、落穂・松笠などうち煙りたる草の庵しづかに住なし、いかなる人とは知るられずながら、まづなつかしく立ち寄ほどに、月、海にうつりて、昼のながめまた改む。江上に帰りて宿を求れば、窓をひらき二階を作りて、風雲の中に旅寝するこそ、あやしきまで妙なる心地はせらるれ。
松島や鶴に身をかれほとゝぎす 曾良
予は口をとぢて眠らんとして寝ねられず。旧庵をわかるる時、素堂、松島の詩あり。原安適、松が浦島の和歌を贈らる。袋を解きて、今宵の友とす。且つ、杉風・濁子が発句あり。
どうであろうか?芭蕉はこの松島の絶景を描写するに漢詩文を援用している。もちろん芭蕉は実際の漢詩文に登場する景色を見たことはない。あくまで文章の上で知っているに過ぎない。「洞庭・西湖」「浙江」を登場させ、杜甫や蘇東坡の詩(「児孫愛す」・「美人の顔を粧ふ」)を援用しているのだ。これが芭蕉の情景描写の特徴と言える。他の所の情景描写でも歴史的な故事や歌枕などを紹介するに過ぎないように思える箇所が多い。しかもこの絶景を目の前のして「口をとぢて」と言って句作をしていない。句は同行者曾良のものだ。この作品は、芭蕉が色々な場所を訪れ、その景色に感動し、句作をしていく記録では、けっしてないということだ。芭蕉のこの作品を近代的な「写生」といった概念で読むこと自体が無理なのかもしれない。
では、この旅はどんな旅だったのか。この作品は実は実際の旅から数年経ってからまとめられたと言われている。つまりは実際の旅の記録そのままではない。それでもこの作品からも窺えるのが、まずはとてつもなく長い旅だったことだ。そして一つところにかなり長居をしている旅だと言えることだ。この旅は4月から9月まで約半年にわたっている。しかも例えば4月には那須の黒羽に13泊もしているし、5月には出羽尾花沢に10泊、6月羽黒山に7泊・酒田9泊、7月金沢9泊、山中温泉に8月にかけて8泊、そして9月にかけて最後の地美濃大垣には14泊もしている。そしてその各地で俳諧を興行しているのだ。実はその各地には芭蕉に心酔する門人たちがいたわけだ。この頃の芭蕉はすでに全国に多くの門人というか、俳諧でいう連衆を抱えていたのだ。しかもその門人たちは各地の有力者たちである。当時、一老人芭蕉が一人の同行者を連れただけでこれだけの旅をできたのはこうした背景があったからだと言える。こういうと文学作品に対して現実的な要素を指摘しすぎると面白くはないかもしれない。しかし芭蕉がいかに自分の俳諧の道を苦労して切り開いたかの記録として読めば、けっしてうがった味方ということにはならないと思う。
その三 書簡
書簡は28篇収められている。実兄に宛てた一通以外は全て門人に宛てた書簡である。これらの書簡には、芭蕉が新しい俳諧の形を切り開き、それをいわば全国展開することにいかに執心していたかが窺えて、興味深い。以下二つの書簡を取り上げる。
- 三二 立花牧童(彦三郎)宛書簡 四十七歳
- 五五 杉山杉風(市兵衛)宛書簡 五十一歳
立花牧童(彦三郎)宛書簡
立花牧童という人は加賀金沢の人で、奥羽行脚の旅の途中で芭蕉の門に入った人物。後に兄の北枝とともに加賀蕉門の中心的存在となる。この書簡は、牧童の消息を聞き、書簡ももらったから、その返事だという体裁で、しかも金沢に大火事があったとのことで、そのお見舞いという内容だ。しかし、注目すべきは以下の文言だ。
(前略)いよいよ御はげみなさるべく候。世間ともに古び候により、少々愚案工夫これ有り候て、心を尽し申し候。その段ほぼ乙州も心得申し候あひだ、御話なさるべく候。
火事があったが句会も行われているようなので、ぜひ励んで欲しいといい、最近俳諧が停滞しているが、そのことに対して自分には或考えがあるので、そのことをよく知っている弟子の乙州によく聞いてくれと言っている点だ。この「愚案工夫」というのが、所謂「軽み」と称される蕉門の新しい俳諧の形で、これを全国へ広げたい芭蕉の意欲がこの書簡に感じられる。
杉山杉風(市兵衛)宛書簡
杉山杉風は江戸の門人。芭蕉庵を提供した人物でもある。この書簡は芭蕉が膳所の無名庵に滞在している頃、『別座鋪』という江戸で刊行された選集についての様々な点について杉風に諭しているものだ。『別座鋪』という選集は子珊という人物が杉風と桃隣という人物(芭蕉の縁者と言われている)の協力によって刊行されたもので、芭蕉の晩年の傾向、すなわち「軽み」を示す選集として、また停滞した俳諧を打開するものとして、大いに評判になった。しかし一方ではこれを良しとしない向き(嵐雪や其角)もあったので、蕉門分裂の引き金にもなったという。また、その『別座鋪』刊行に際しても、版下を杉風に見せなかったとか、同じ江戸蕉門の野坡や利牛の作品を載せていないとか色々手違いがあったようで、それについて師匠芭蕉は杉風になんやかやと取りなしている。ここで芭蕉は門人の誰それを非難するようなことは一切言っていない。むしろ「この新傾向をしっかりやりなさい」といい、この新傾向を非難する向きには「相手にするな」と言っている。
まづ「軽み」と「興」ともつぱらに御励み、人人にも御申しなさるべく候。
と結んでいる。いかに芭蕉が蕉門の新傾向の普及と定着に心血を捧げていたがわかる書簡だ。
その四 遺書
遺書と思われるのは実兄に宛てた書簡と門人支考に口述を筆記させたもの3通がある。ただ、兄に宛てた遺書は極めて簡潔なもので、「ここに至って(死を覚悟していること)何もいうことはない。皆さんよろしく」としか言っていない。いかにも芭蕉らしいと言っていい。
支考が口述を筆記したものの1通目は遺品の所在や移譲について触れ、作品の誤伝訂正の依頼だ。
2通目は江戸深川の芭蕉庵ゆかりの人々への訣別が内容だが、特に桃隣に対する心配が際立っている。桃隣は芭蕉の親類筋というが、当時の営利的な点取俳諧を志向しているらしく、それを心配し、杉風らに指導するよう頼んでいる。それに支考の深切に対する謝辞だ。
3通目は遠隔地にいる古参の門人たちに対する訣別。この中で「いよいよ俳諧御つとめて候て、」という言葉が繰り返されている。最後に其角・嵐雪に対する言葉も忘れていない。最後まで芭蕉は自分が人生を賭けて唱導し、広げてきた蕉風俳諧というものに固執していたのがよくわかる。
この3通目は元禄7年10月10日に書かれたという。その翌々日12日に芭蕉はその俳諧一条に生きた生涯を閉じた。
終わりに
こうしてこの書に収めらた芭蕉が書き残した文書を読んでいくと、いかに芭蕉が俳諧の新しいあり方を求めて奮闘していたがよくわかる。ただ、その俳諧は今やほとんど失われてしまったのが残念でならない。芭蕉を近代的な解釈から解放して、芭蕉が求め、実現してきた世界を甦らせることができたらどんなにか素晴らしいかと思う。それにはもっと芭蕉やその連衆たちの俳諧を読まなければならい。今回はここまでとする。
2024.03.22 この項了